JOJOVELLER Stand Guide Commentaries
Interview Archive
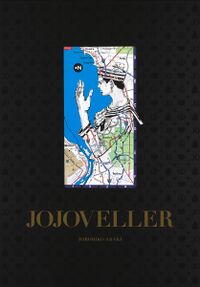
Interviews with Hirohiko Araki's various editors, and a collection of brief commentary from Araki about each interview. These were published in the History book in JOJOVELLER, released on September 19, 2013.
Interviews
Q: So, you took over as editor after Mr. Kabashima.
Sasaki: I believe I took over as editor when I received the manuscript for the final chapter of Part 3. Kabashima was promoted to deputy editor-in-chief of Super Jump, so that led to a change in responsibility.
Q: So, was that the first time you met Araki-sensei?
Sasaki: No, it was back when Part 1 was being serialized. Araki-sensei often came to the editorial department, so it was during that time. Back then, the word "ikemen" (good-looking guy) didn't exist, so we were saying things like, "Is that Araki-sensei? He's super 'hansamu'!"[a] His clothing was neat and stylish, and his physique was slender, too. But considering the kind of manga he was drawing (laughs), I thought, "Maybe he's a strange person?" But when I actually talked to him, I found out he was a really nice person, you know? I was surprised by the contrast. Even now, nearly 30 years later, I remember it vividly.
Q: At that time, how was Araki-sensei viewed within the editorial department?
Sasaki: Both Cool Shock B.T. and Baoh the Visitor weren't huge hits, but they had a niche fanbase and were considered very unique works. Araki-sensei was a writer with a lot of quirks, and it was quite challenging to bring his specific style into the mainstream. However, with Part 1, Part 2, and then Part 3, he managed to make JoJo a massive hit. From my perspective as a junior, it seemed that it was the combination of Araki-sensei and Mr. Kabashima that made that possible. They were an amazing team, and succeeding Kabashima as editor put tremendous pressure on me (laughs). On the other hand, I was happy that I was given the job after Kabashima. I was a huge fan of JoJo, but at that time, Weekly Shonen Jump (hereafter Jump) had popular works such as Dragon Ball, Slam Dunk, and Yu Yu Hakusho, and JoJo stood out among them.
Q: In your experience as editor, what was your impression of Sensei?
Sasaki: Originally, what I heard from Kabashima was that Araki-sensei liked Western music and horror movies, but I don't listen to Western music and I hate horror movies because they're scary (laughs). However, I do love overseas drama series, like the TV show Twin Peaks at that time. Araki-sensei also liked those kind of shows, so we often talked about foreign dramas.
In terms of our interactions at that time, the process was that his manuscripts would be sent via fax, and then we would have discussions over the phone. But I found it easier to talk face-to-face, so when I would suggest, "I'll come over," he'd always say, "No, please don't come." I guess he preferred to think on his own and had a rhythm of working that would be disrupted by meeting people. That's why he asked me not to visit.
Also, his schedule management skills were amazing. Even now, but certainly back then, he was incredibly on the mark with his submissions and never missed deadlines. A week before the actual deadline, his manuscript would be handed over to our staff for finishing touches.
During that time, Araki-sensei and I would go out for dinner, always at a nearby Italian restaurant. We never discussed manga during those dinners. Araki-sensei and I both love Italy, so we only talked about that. After dinner, we would go to a family restaurant called Jonathan's and have a meeting for about an hour, and after that we really just chatted. I don't remember the specific details, but it was probably about foreign dramas. After chatting, we would return to the workplace where Araki-sensei would check the manuscript that our staff had completed and give it to me. That was the rhythm of our routine.
Q: It was exactly the same as when Kabashima was the editor.
Sasaki: What surprised me when I first received his manuscripts was when he asked, "Are there any issues?" When I replied that there was nothing wrong with the manuscript, he said, "No, there has to be something, right?" and I was like, "Huh?" (laughs). After that, every time I received a manuscript, he would ask me to correct something. That might have been a sort of superstition, or even a ritual of his.
Q: Is the fact that his schedule was so organized something you appreciated as an editor?
Sasaki: This might not be the right way to put it, but physically, it was very easy for me. I never lost my rhythm, which made it easy for me to plan as an editor. Even with the first JoJo artbook, JoJo 6251, which was my responsibility, it was very easy to plan.
Q: JoJo 6251 included both illustrations and articles explaining the characters, making it a precursor to what would now be called a fan book.
Sasaki: Since Araki's work has a ton of hardcore fans, we decided to create something a bit different and more interesting from a typical artbook.
Q: You were in charge from the end of Part 3 to the middle of Part 4. How did the development of Part 4 begin?
Sasaki: Great authors, without exception, are people who can create extremely powerful enemies. While the protagonist is a reflection of the author and can be created to some extent, creating a compelling antagonist requires real talent. In other words, this is where Sensei's skill shines. From Part 1 through Part 3, there was an epic saga with DIO, one of the most memorable enemies in Jump's history. So when I began to wonder what kind of powerful and amazing villain would be created for Part 4, I was told that Part 4 was to be set in Japan, specifically Sendai, and I thought, "Huh?" (laughs).
Q: So it wasn't a "power-level game" for introducing stronger villains, was it?
Sasaki: I remember being surprised when I heard Sensei say, "I want to make it a mysterious town" and "I want to make a map of the town," and I started thinking, "So, Sensei is creating such detailed drafts as well." It was impressive to see the shift from the fantastical elements of Part 2, to the road-movie format of Part 3, to wanting to draw a whole world confined to such a limited location in Part 4. The variety of ideas was astonishing.
While Part 3 made a huge impact and gained major popularity, it seems that Sensei's talent shines brighter when more focus and spotlight is on him, and I think Sensei significantly went up several notches as an artist during the serialization of Part 3. It was also interesting to hear him discuss the various ways of fighting in such a small city setting. For example, Koichi's Stand, which is based on handwritten characters (both katakana and kanji), really confused me. Sensei mentioned, "I think if these handwritten characters could, you know, be absorbed somehow, it would be cool," and I was like, "Huh?" (laughs). I didn't understand at all, so he made the name Echoes for it and I thought, "I see!"
Q: When Part 4 began, was there any talk of Kira, the main antagonist?
Sasaki: No, we didn't talk about future developments at that time. By the time Kira appeared, Kaito was the editor, so it's better to ask him.
Personally, my favorite was Tonio's Stand, Pearl Jam. Araki would say things like, "I want to eat this Italian food," and "I hope it cures my back pain, too," while creating him. And then there was Yukako Yamagishi... At that time, I don't even think the word "stalker" existed yet, but it was such a scary thing that could happen to anyone in everyday life.
Q: I think that Part 4 has a lot of unique characters like that.
Sasaki: Rohan Kishibe is kind of similar to Sensei in some ways. Rohan is a character who believes that "anything is permissible for the sake of drawing good manga," and Sensei is someone who is also incredibly dedicated to create good manga.
Q: Part 4 is structured around short story arcs that are connected by the theme of a serial killer. Were there any major concepts in place at the start of production?
Sasaki: Hmm, there might have been something... I think the concept of Part 4 was originally related to Nostradamus's prophecies, which is why the story is set in 1999.[b] The original storyline might have been like "What emerges from Morioh will decide the course of the next century." Of course, the final storyline that you saw three years later was more interesting (laughs).
Q: Ah! So the major storyline involving Kira was developed throughout the serialization of Part 4. Did you or the editorial department give Araki-sensei any orders during the production of Part 4?
Sasaki: No, not when it came to JoJo. Specifically regarding my part, I never ordered anything like, "Let's introduce a major antagonist right now."
Q: Josuke's Stand ability is the ability to heal things, and it seems relatively plain compared to Star Platinum. What do you think about that?
Sasaki: When I first heard about that, I definitely thought, "How will this work in battles? It might be difficult." However, Araki-sensei already had so many ideas about how the battles would work, and I thought, "He really had it all planned out." Since Part 3 was filled with an endless series of Stand battles, the ability to heal things might have been a reaction to that. At the end of the day, both Josuke and Tonio had peaceful and kind Stands.
Q: How did readers respond to Part 4?
Sasaki: In terms of age, it was definitely more older readers. It seems that there were more young adult (seinen) readers rather than young boy (shōnen) readers.
Q: Had you read any of Araki's work before you became his editor?
Sasaki: I read all of them in real time. As I mentioned earlier, I was really surprised when I first met Sensei because he seemed like a very ordinary and nice guy. On the other hand, considering that he was doing a weekly serialized manga while leading a perfectly normal life, I thought, "That's incredible."
Despite managing such a detailed weekly serialization, he takes many breaks and even travels to Italy several times a year. His ability to maintain such a normal lifestyle is impressive. It's amazing how normal he is. This is true for other writers as well, but the dedication Sensei puts into his work, to the point where he becomes oblivious to his surroundings, is something beyond normal.
Q: As the editor, why do you think JoJo has been able to continue for so long?
Sasaki: The key is that Sensei's ideas never run out. To put it more specifically, it's about his immense amount of endless input. Speaking of long-running series like JoJo, you can make a comparison to Osamu Akimoto, the creator of KochiKame.
Akimoto-sensei is a genius of curiosity. While most people might become disinterested or find things tedious as they age, Akimoto-sensei has maintained a pure curiosity, which is the driving force behind KochiKame. Araki-sensei is exactly the same! His insatiable curiosity and willingness to incorporate new things, whether from film or fashion, is his secret. The human mind has its limits, and ideas can wither away within five years. By constantly bringing in new influences, immersing in them, and keeping them as ideas, Araki-sensei and Akimoto-sensei are remarkably similar despite working on completely different stories.
Q: After Part 4, JoJo continued with Parts 5 and 6. At that time, you were still working at Jump's editorial department. Do you know what the response of the readers were like?
Sasaki: The results of reader surveys are actually just numbers. What's important is how you interpret those numbers. So, even if the survey scores are low, it's crucial to look at which age groups responded to understand the actual popularity of the work. In that regard, JoJo was never the top rated series, but it was definitely a flagship work for Jump.
As a side note, personally, I wanted to read new works by Araki-sensei other than JoJo, such as a one-shot like Gorgeous Irene. But at one point, Sensei said he "would only draw JoJo," and I thought, "Oh, that's a shame."
Q: After Part 6, JoJo transitioned to an irregular serialization format in Jump for the seventh part, Steel Ball Run, and later moved to Ultra Jump (hereafter U-Jump). You were one of the few editors who closely observed this transition.
Sasaki: Regarding the irregular serialization of Part 7, I think there was a feeling that the weekly pace suited for young readers no longer worked for JoJo. Also, Jump itself was no longer adhering to the rule that writers “must publish a chapter every week,” and there was a trend toward allowing various serialization styles. They were not giving veteran creators strict deadlines either. That's likely why the irregular serialization format was adopted.
At the time of the move to U-Jump, I had become deputy editor-in-chief, but around the end of Part 6, the style of JoJo was drifting away from Jump's core young-boy demographic. I think another reason was that the age of JoJo fans was no longer the main focus of Jump. So, at Araki-sensei's request, the transition to U-Jump was made. I believe that to elevate JoJo to the next stage, it was necessary to move away from Jump, allowing Araki-sensei a time to let his work graduate.
Q: From the perspective of a former editor, what do you think are the charms of JoJo and Araki's style?
Sasaki: It is one-of-a-kind, with many elements that you can't find anywhere else. The delivery of dialogue, the plot development, the panel composition, the way poses are meticulously crafted - everything is unique to JoJo. This uniqueness is what makes JoJo "JoJo." Not just in manga, but within all major series, there is an originality that Araki has that is impossible to imitate.
Q: That's especially true for Stands. No one can imitate them.
Sasaki: It's an invention. When you say "giving form to psychic powers," it makes sense. You can picture it. But back then, no one had thought of it. Now, if someone tried to do something even remotely similar, people will definitely say, "That's a Stand." It's a one-of-a-kind work.
――佐々木さんは椛島さんから引き継いで担当されたわけですね。
★たしか第3部の最終回の原稿をもらう時に引き継ぎをしたと思います。椛島が「スーパージャンプ」の副編集長に昇進するので、それにともなっての担当変更でした。
――では先生との出会いは、引き継ぎが初めて?
★いや、第1部を連載されている頃、先生はよく編集部にいらっしゃっていたので、その時に。当時はイケメンなんて言葉はなかったので、僕らは「あれが荒木先生?」「超ハンサムじゃん」とか言ってました。服装も小綺麗というかオシャレで、体型もスマートだし。でも描いてる漫画がああでしたから (笑)、「変な人なのかな」と思いつつ話をしてみると、すごく普通に良い人じゃない? そのギャップに驚きました。30年近くたった今でも鮮明に憶えています。
――当時、編集部の中で荒木先生はどんな作家と見られていたんでしょうか?
★『魔少年ビーティー』も『バオー来訪者』も大ヒットじゃないけどマニアックなファンを持つ、すごく特殊な作家さんだったわけです。クセの多いところも含めて才能を活かしたままメジャーに持っていくのは相当難しいタイプの作家さんなんですが、それが第1部、第2部と来て、第3部で『ジョジョ』を大ブレイクさせていた。それは荒木先生と椛島のコンビだからできたんじゃないか、と後輩の立場からは見ていました。僕らから見てもすごいコンビだったわけで、そのあとを自分が担当するんだからものすごいプレッシャーだったわけ (笑)。その反面、椛島のあとを任されたということは嬉しくもありましたね。『ジョジョ』が大好きだったってこともあるけど、当時の「週刊少年ジャンプ」(以下、WJ) は『ドラゴンボール』や『スラムダンク』、『幽☆遊☆白書』といった人気作があって、その中でも異彩を放っている『ジョジョ』ですから。
――実際に担当されて、先生の印象は?
★そもそも椛島から聞いていたのは「洋楽好き」「ホラー映画好き」だったけど、僕は洋楽聴かない、ホラー映画は怖くて嫌いという (笑)。ただ海外ミステリーものは大好きで、例えば当時だと『ツイン・ピークス』というテレビドラマシリーズとかね。その辺も先生はお好きだっていうことで、先生とよく海外ドラマの話はしていました。で、当時のやりとりでいうと、ネームのFAXが来て電話で打ち合わせとなるわけです。でも僕は面と向かって直接話すほうがやりやすかったんで「僕、行きますよ」って言ったら「いや、来ないでくれ」と。ひとりで考えたいというか、そういうリズムになっているんでしょうね。だから人と会うとそのリズムが狂うから「来ないでくれ」ということでした。それとすごかったのがスケジュール管理能力ですね。今もそうかもしれないけど、当時からとにかく原稿のアップが早くて遅れない人だった。本来の締切前週の木曜日の夕方には先生の手を離れてスタッフが仕上げ作業。その間に僕と先生は食事に出かけていたんですが、場所は決まって近くのイタリアンレストラン。その間は漫画の話は一切しない。先生はイタリア好きですが、僕もイタリアが大好きだったから、そういった話ばかりでしたね。で、食事が終わるとおもむろにファミレスのジョナサンに移動して1時間くらい打ち合わせをバーッとして、そのあとは本当に雑談でした。具体的な内容は憶えていないけど、たぶん海外ドラマとかの話かな。その雑談もひととおり終わって仕事場に戻って、スタッフの仕上げが終わった原稿を先生がチェックして僕に渡してくれるっていうリズムです。
――椛島さんの時とまったく同じですね。
★最初に原稿を渡された時に驚いたのが「何か修正とかないですか?」って聞かれたことですね。原稿に問題はないと返事をしたら「いや、何かあるでしょ?」とまた言われて「え?」って (笑)。その後も原稿を受け取る時には、何か直していただくというのは毎回ありました。あれは先生の一種のジンクスというか、儀式みたいなものかもしれないですね。
――スケジュールがしっかりしている点は、編集者としては有り難いこと?
★言い方は悪いかもしれませんが、肉体的にはすごく楽でした。リズムがまったく崩れないのは編集としても予定が立てやすいわけで、最初の画集の「JOJO6251」も僕の担当だけど、そういう本の企画も立てやすかった。
――「JOJO6251」はイラストに加えてキャラ解説記事があったりして、今でいうファンブック的なものの走りですね。
★荒木作品はコアな読者が多かったので「普通の画集とはちょっと違う面白いものを作りましょう」という話になったんですよ。
――第3部のラストから第4部の途中までの担当が佐々木さんですが、第4部の立ち上げはどういった流れだったんでしょうか。
★偉大な作家さんは例外なく、ものすごく強い敵を作れる人なわけです。主人公は作家自身の投影だからある程度は作れたとしても魅力的な敵キャラは才能がないと作れないし、逆に言えばそこで作家さんの才能が現れるわけです。で、第1部から第3部は壮大なサーガともいえる物語で、DIOもWJ史上に残る敵だった。そのあとの第4部でどんな強くてすごい敵を考えているのかと思っていたら、第4部の舞台は日本、しかも仙台って言われて「え?」って (笑)。
――「より強い敵を出す」というパワーゲームの構図ではなかったわけですね。
★「ミステリアスな街にしたい」「街の地図を作っていきたい」という話も聞いて、「先生はこういうことも考えているのか」とも驚いた記憶がありますね。第2部みたいに不思議なものを描いて第3部のロードムービーも描けて、第4部では場所を限定した世界も描こうっていう。その引き出しの多さには驚かされました。第3部で大きくメジャーになったという点もあるでしょうが、才能は当たるスポットライトの量が多ければ多いほど輝いていくわけで、おそらく、第3部の連載中に作家としてのステージを何段も上がったんだと思います。街という小さな舞台で色々な戦い方をするという話を聞くのも面白かったですね。康一のスタンドも描き文字のスタンドなんだけど、先生から「描き文字がね、なんか染み込んだら面白いと思うんだよねー」って言われて「?」(笑)。ちょっと意味が分からなくてネームにしてもらったら「なるほど!」と。
――第4部立ち上げの際に、ラスボスである吉良の話は出ていましたか?
★いや、先のことは話していませんでした。吉良が出てくる頃は垣内が担当だから彼に聞いてもらったほうがいいですね。僕が個人的に好きだったのは、トニオのスタンドのパール・ジャムです。「このイタ飯、食べたいっすね」「腰痛も治してくれないかなー」なんて話をしてましたね。あとは山岸由花子かな。当時はまだストーカーという言葉も無かった気がしますが、生活に密着した怖さがありましたね。
――第4部はそういった個性的なキャラクターが数多く出ますね。
★岸辺露伴は先生と似ているところがありますね。露伴は「良い漫画を描くため。そのためならすべて許される」というキャラクターですが、先生も良い漫画を描くことに一生懸命な人ですから。
――第4部は短いエピソードを殺人鬼という縦の串で通すという構成なんですが、立ち上げの時に何か大きな設定とか構想はあったんでしょうか。
★何かあったかなあ…。ノストラダムスの予言にからんだ設定は聞いた気がしますね、だから年代設定が1999年だっていう。「次の100年を支配する何かが杜王町にあって」といった感じだったかもしれない。でも実際は全然違うよね (笑)。週刊連載はね、最初に最終回を考えていても描いているうちに作家も成長していくから、どんどん変わっちゃうことも多いです。そりゃあ3年後に考えた最終回の方が面白いに決まってますからね。
――第4部で言うなら、短いエピソードの積み重ねの中で吉良という大きな流れも出来たわけですね。
――編集部や佐々木さんからの、先生に対するオーダーはあったんでしょうか。
★『ジョジョ』に関してはないですね。僕の担当分に限っていえば、「ここらで大きな敵を出しましょう」とか、そういったことは言っていません。
――仗助の「ものを治す」というスタンド能力はスタープラチナに比べると、地味な印象を受けるんですがその辺は?
★そこは最初に聞いた時に「どうやって戦うんだろう?」「難しいかもしれない」というのはたしかにありました。ただ、先生から「こういう戦い方をしますよ」というアイデアがバンバン出てきて、「ちゃんと見越して考えていたのか」と思いましたね。第3部は戦いの連続だったので、「ものを治す」というのはそれの反動だったのかもしれない。仗助にしろトニオにしろ、平和なスタンド、優しいスタンドですから。
――第4部は読者の反応はどうでしたか。
★年齢層で言うと、やはり高めの読者が多かったですね。少年というよりは青年に近い年齢層の男子が多かったんじゃないかな。
――担当されていた中で、先生の特徴的な印象に残ることは?
★締切もそうだけど、約束の時間には絶対に遅れないってのはありますね。リズムを崩さないというか。だからこちらも、当たり前のことではあるんだけど時間は厳守してました。時間に遅れたからといって怒るような人でもないんだけど、作家さんがそこまできっちりやってくださるわけだから、締切を守れって言ってる立場の僕らはそれ以上にきちんとやらなきゃね。
――荒木作品は担当前から読んでいたんですか?
★全部、リアルタイムで読んでいました。最初にも言いましたが、初めて会った時はごくごく普通の感じのいい人でしたから本当に驚きました。ただ、逆に言うと超多忙なはずの週刊連載をしていながら常人以上に規則正しい普通の生活を送っているので、「そっちのほうがスゲエ」と思います。週刊連載であれだけ緻密な構成をして緻密な絵を描いてオリジナリティにあふれる作品を出しつつ、きっちり休みは取って年に何回かはイタリアに行く。その普通っぷりがすごい。他の作家さんにも言えることだけど、気持ちが入ったら周囲が見えなくなるほどの集中力があり、それを維持しているだけでも常人離れしているのにね。
――編集者という立場から、『ジョジョ』が長く続けられる理由はどこだと思いますか?
★アイデアが枯渇しないこと。もっと言うと、インプットの量が半端ないってことですね。『ジョジョ』と同じく長く続いているという点で『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の秋本治先生の話になりますが、秋本先生は何の天才なのかというと好奇心の天才なんです。普通の人であればある程度の年齢になれば、色々と冷めてきたり面倒と思ってしまうはずなんですが、秋本先生は純粋な好奇心を持ち続けていて、そこが『こち亀』という作品の原動力になっている。荒木先生もまったく同じで映画でもファッションでも、新しいものを取り入れていくどん欲さが秘訣だと思いますね。だって人間の頭の中から出るものなんて限りがあって、5年で枯れますから。ちゃんと絶えず新しいものを入れて、自分の中で咀嚼してアイデアとして持ち続けられるという点で、描いている作品はまったく違いますが秋本先生と荒木先生はものすごく似ていると思います。
――第4部のあとも『ジョジョ』の連載は第5部、第6部と続きました。その頃も佐々木さんはWJ編集部に在籍していたわけですが、読者の反応はどうだったんでしょうか。
★読者アンケートの結果は、実はただの数字なんです。大切なのは、その数字をどう読むか。だから例えばアンケートが低かったとして、それがどの年齢層にどう受けたのかという点をちゃんと見た上で、作品の実際の人気を読み取るのも編集の仕事なんです。その点でいくと『ジョジョ』は、トップを走る作品じゃないけど間違いなくWJの看板作品でした。余談ですが僕個人の気持ちでいうと『ジョジョ』以外の作品、例えば『ゴージャス☆アイリン』みたいな作品も読みたいなと思っていましたが、ある時期から先生は「『ジョジョ』しか描かない」といったことを言ってらして、「そうなんだ、勿体ないな」と思っていたことはあります。
――第6部のあと、第7部である『スティール・ボール・ラン』はWJで不定期連載という形に掲載スタイルが変わり、途中で「ウルトラジャンプ」(以下、UJ) に連載の場を移しました。佐々木さんはそれをずっと間近で見ていた数少ない編集者のひとりになります。
★第7部の不定期連載については、先生の中で少年向けの週刊連載というペースが『ジョジョ』に合わなくなってきているんじゃないか、という気持ちもあったと思います。合わせてWJ自身もかつてのように「毎週絶対載せる」というスタイルではなくなっていて、いろいろな連載スタイルがあってもいいのでは、という流れでした。ベテランの作家さんに対しては杓子定規な接し方もしていなかったし。それで不定期連載という流れになったはずです。移籍の時は僕は副編集長になっていましたが、第6部が終わったあたりで作品も作風もWJ本来の少年読者から離れつつあったんでしょうね。荒木ファンの年代がWJのメインどころではなくなってきていたという点もあったと思います。それで荒木先生からの要望もあってUJに移籍という形になりました。『ジョジョ』を次のステージに上げるには少なくとも舞台はWJではないだろうし卒業の時期だったんだろうと思っています。
――歴代の担当編集者という立場から見て『ジョジョ』と荒木作品の魅力はどこでしょうか。
★ワン&オンリー感、他では読めないものがいっぱいあるっていうことですね。セリフ回し、展開、コマの構成、ポーズの取り方、すべてが他の漫画では見られなくて、それが『ジョジョ』を『ジョジョ』たらしめている。漫画に限らず大ヒット作はすべてそうなんですが、オリジナリティに関しては誰も真似できないものがあります。
――特にスタンドはそうですよね。誰も真似できない。
★発明ですね。「超能力を形にする」って言われてみればそうなんだけど、それまで誰も思いつかなかったし、今それをやったら「スタンドだね」と絶対言われてしまう。そういうワン&オンリーの作品ですね。
――垣内さんが担当されたのは、どこからなんでしょうか。
★第4部を佐々木から引き継いで、レッド・ホット・チリ・ペッパー戦からハイウェイ・スターが終わるところあたりまでが担当です。いちばん最初の打ち合わせの時、先生は「『ジョジョ』はスタンドのアイデアがいっぱいあるから、長くやりたいんだよね」といったことを言っていました。
――第4部は舞台が日本の杜王町なんですが、佐々木さんへの取材によると「杜王町にはノストラダムスの予言に絡んだ何かがある」という設定が当初あったらしいんですが。
★ああ、たしかに佐々木から「杜王町の地下に遺跡があるらしいんだよ」といった設定は聞いた記憶があります。でも私が最初に担当したレッチリ戦で、ザ・ハンドが地面を削ったら出てきたのは電気ケーブルだったので (笑)、荒木先生はもう古代遺跡の設定とかをやる気はないのかもしれない、とは思っていました。週刊連載は変わっていくものなんですよ。第4部は先生が吉良というキャラクターを見つけたことで、いろんなことが決まったんだと思います。
――垣内さんの担当時代にラスボスの吉良が登場しましたね。
★杉本鈴美のエピソードで殺人鬼 (吉良) の存在が明らかになるんですが、先生も私も怪談にはまっていた時期だったので、当初はそれっぽい幽霊のエピソードを何回か短くやろうというレベルだったんですよ。それで杉本鈴美のエピソードが始まって3週目の打ち合わせの時に、先生が突然「この街に殺人鬼がいるのって面白いよね?」って言い出したんです。あの日の打ち合わせはすごく楽しそうで「思いついたんだよ!殺人鬼だよ!!」「鈴美を殺した犯人をラスボスにしたい!」と。はっきりと「ラスボス」と言ったのも憶えています。吉良を出すのが決まったタイミングはそこですね。
――吉良について「週刊少年ジャンプ」(以下、WJ) 編集部の反応はどうでしたか?
★実は当時、編集部のみんなから「DIO以上の敵が出てこない。どうなっているんだ」ということは言われていました。でも先生と話をしても「DIOより強い敵を出しても、それは単なる強さのインフレでしかない。『ジョジョ』は違うから」という返事でしたね。なので私は正直、「第4部はラスボスが出ないままかもしれない。中ボスを倒しながら杜王町の地図が完成して終わるのかな」と思っていました。だからラスボスの話が出た時に、「ついに来た!!」というのは自分の中でありましたね。しかも街という身近な世界で敵が殺人鬼。いいですよね。
――先生の中では、吉良をどういったスタンスの敵にしようと考えていたのでしょうか。
★「第3部のDIOは主人公の動きを遮ろうというタイプ。だから第4部は逆に陰に潜んでいて、見つかったら攻撃してくるというラスボスにしたい」というのは言っていました。それと殺人鬼のアイデアが出た当初は「いろんなところに爆弾が仕掛けてある」「主人公はそれを避けながら敵を追いつめなきゃいけない」という話でしたね。
――サスペンスを描きやすい設定ですね。
★吉良のシアーハートアタックのエピソードでは仗助たちが吉良と接触するという展開なんですが、最初は康一くんがシアーハートアタックの動きを封じただけで終わる予定だったんです。展開の途中で先生から「仗助たちと吉良が出会っちゃうのどう?」というアイデアが出たんですが、そこは編集者の立場から言うとラスボスと出会ったら普通は最終対決になるわけで、「あれ? 第4部はこれで終わるの?」という心配はありました。だから当時の漫画の扉に、「第4部
――吉良が登場して以降、第4部は大きく流れが変わりましたね。
★吉良を描くにつれて先生は「吉良の能力をバージョンアップさせたい」とは言っていました。吉良は爆弾能力なので「だとしたら酸素だろう」というところは打ち合わせで決めて、そこで出来たのが
――吉良の第3の爆弾であるキラークイーン バイツァ・ダストのアイデアも先生の中には当初からあったんでしょうか?
★その辺は関谷が担当の時代なので分かりませんが、時間が繰り返すアイデアそのものの話は私の時代に雑談レベルではしていました。ただ吉良の能力と決めていたわけではなく、スタンド能力のアイデアのひとつだったと記憶しています。「敵を『時間の輪』に閉じこめて、先に進めなくするスタンドの話は出来ないか?」という感じでしたね。ただ「19ページの週刊連載で『時間の輪』を表現するのは不可能じゃないか」という理由で保留にしていたんですよ。それが吉良の能力になって成立した点は、荒木先生のストーリー展開の巧みさとアイデアのすごさだと思いましたね。余談ですが私は荒木先生は、「時間フェチ」なところがあるんじゃないかなと思っています。DIOにしても吉良にしても、第5部のディアボロにしても、ラスボスの多くはみんな「時間」ですから。
――キラークイーンはシンプルでありながら存在感も放つデザインのスタンドですが、スタンドのビジュアルについて編集者は何か関わったりしているのでしょうか?
★特にはないですね。キラークイーン以外も含めて、スタンドのデザインは原稿があがるまで私も分からないんです。ネームの時には大きなマルに「スタンド」って描いてあるだけなんですよ (笑)。だから原稿でいちばんに見られる喜びはあります。
――第4部連載当時の読者の反応はどうだったんでしょうか。
★読者的には日本人の主人公で舞台も日本という身近な設定でもあり、第4部は全体的にアンケートの結果も良かった印象がありますね。
――第4部はスタンド能力の組合せや各キャラクターとの関係性など、色々と先生も工夫していたんじゃないでしょうか?
★いろんなパターンがありましたね。主人公周りの人間関係でいうと、例えば「康一くんが承太郎を尊敬する話にしよう」というテーマの時もあれば、「こんな変な敵を出したいね」という時もあり、あるいは鈴美の時のような「幽霊道路に紛れ込む」というシチュエーションもあれば…、という感じで自由というかフリーダムというか…。当時の先生のインタビューを読むと分かるはずですが「思いついたことを、日記のような感じで描いていきたい」ということでした。当時の先生がやりたかったのがサスペンスで、じゃあどんな種類のサスペンスなのかを毎回探っていくという感じでした。
――第4部には多くのキャラクターが登場します。先生が特に入れ込んでいたキャラクターは誰でしたか?
★重ちーですね。途中で死んでしまうキャラクターなんだけど、先生は最後の最後まで「重ちーを殺すしかないんだけど、殺したくない」と悩んでいました。ただ、そこは吉良との絡みで誰かが死なないと吉良への怒りが沸きませんから、編集者として冷徹に「殺すべきです」と背中を押しました。重ちーが悲しい死に方をしたあとも、先生は「殺さなきゃよかった」と言ってましたから、重ちーは相当好きだったみたいですね。
――重ちーもそうなんですが、第4部は変わった性格のキャラクターが数多く登場するという印象があります。
★宇宙人かどうかも分からない支倉未起隆というキャラクターもいましたね。あれはファミレスのジョナサンでの打ち合わせの前の雑談で宇宙人の話になって、そこから3週間くらいにわたって「宇宙人はいるのか、いないのか」で熱く議論してたところから拾っていると思います。先生的には「宇宙人はいる。でも人間と同じ形をしている」という意見でした。先生曰く「人間のフォルムは自然界において完璧だから、宇宙においても知的生命体はこの形にならざるを得ない」という主張でしたが、私は私で「形は環境によって変わるのでは?」といった話をしたり。どうでもいい細かいことも含めて本当にいろんな宇宙人議論をしていましたから、そこから拾えるネタを集めた形かもしれません。それで宇宙人のキャラが出て、劇中でも宇宙人なのか変人なのか答えは出さないままっていう感じでしたから、私の中で第4部は「変な人がいっぱい出てくる漫画」という認識もありました (笑)。
――バラエティに富んだキャラクター陣ですよね。
★ただ、先生が言っていたのは「変わった人たちがそれぞれの立場で出会った時、それぞれの立場を守るために戦わなくちゃいけなくなる。それが戦いの『動機』で、この『動機』がいちばん大事なんだ」というようなことは言っていました。敵とか味方とか善悪ではなく、「どうしてもこいつとは戦わなくちゃいけない」「許せないものがある」とか、そういうことだと思いますね。その点でいうと仗助と露伴って仲が悪い設定ですが、先生の中ではハイウェイ・スターとの戦いのあとで仲直りする予定だったんです。そのためにずっとハイウェイ・スターのエピソードを描いていたのにネームを見たら仲直りしてなくて、「あれっ?いいんですか?」って聞いたら「こいつら無理だったよ。仲直りはできないですよー」って (笑)。そういうところで意表を突く作家さんでもありますね。
――第4部の担当時、先生について何か憶えている印象的なエピソードはありますか?
★担当を引き継いだ時、私への最初の質問が「近所の小さなレンタルビデオ屋の映画、全部観ちゃったんだけど。何かいい映画ありますか?」って。それって私からすると、編集者として引き出せるものの有無を試されていることになるわけで、そこは内心「来た来た!」というのはありました。作家さんを引き継ぐ時の、作家さんの「オーラ」に「負けちゃいけない」という心構えはできていたつもりでしたが、結構ドキドキした瞬間ですね。そこでちょっとズルいのですが、先生が興味なくて観ていなさそうなコメディ映画の中から『裸の銃 (ガン) を持つ男』という映画を挙げたところ、「観ていない」というので切り抜けたわけですが、翌週の打ち合わせで「あの映画、観たよ」と。そこからその映画についての分析が始まったんですが編集としてはそこで食いついていかないと駄目なわけで、あそこで荒木先生の担当としての私の覚悟が固まった印象はありますね。
――編集者から見て、荒木先生はどんな作家だと感じましたか?
★自身に課している要求レベルは高かったですね。そこは常に「自分はWJの『本流』の作家じゃない」「だから人一倍、上を目指さないと駄目なんだ」ということを言ってました。だから打ち合わせをして今週の展開もまとまった、と私が思った瞬間に先生が「これじゃレベルに達していないな」とやり直すことも多かったですね。普通の作品ならOKなレベルのプロットではあったと思うんですが。荒木先生の持論ですが、「ベストセラーの理論」というのがあって、それは例えば「あるアーティストのアルバムで最良の作品はどれか」というと、いちばん売れたアルバムのひとつ前のアルバムだと。なぜかといえば「そのアルバムが良かったから次のアルバムがいちばん売れたんだ」という論理なんです。だから「自分も手を抜いたら来週は良かったとしても再来週くらいには落ちてしまう。いいものを出し続けていくには、ずっと高いレベルでやっていかないといけないんだ」と言っていました。そんな感じで荒木先生は『ジョジョ』という作品を常に「もうひとつ上に行かなきゃいけないんだ」という意識で描いていると思います。
Q: Mr. Sekiya, when did your part as an editor begin?
Sekiya: From the time Stray Cat appeared in Part 4 all the way up to the final chapter. I left around the time we began Part 5. In terms of duration, it was about a year. It should have been around my second year after joining the company.
Q: How did Weekly Shonen Jump (hereafter Jump) readers react to Part 4 at the time?
Sekiya: Mr. Kaito, my predecessor, was in charge when Kira changed his face and made his escape. I think readers were getting excited, wondering, "Is this already the climax of Part 4?!" However, when I took over, neither Josuke nor Jotaro appeared, so the reaction from readers became weaker.
Of course, there were many core JoJo fans, but in terms of the most straightforward reader feedback, like popularity polls, our presence wasn't always visible to a broader audience. I think this is a trend not only for JoJo, but for all long-running serialized works. Even if Araki-sensei didn't care that much about it, as the editor, I still had to pay attention to reader reactions and audience growth.
So, I subtly suggested that he should bring out Jotaro, the popular character. But he dismissed it, saying, "Jotaro stops time, so no one can beat him. That's unfair" (laughs).
While we were going back and forth, the story started to heat up around the episode where Kira and Josuke fought with invisible air bombs, and we were able to conclude Part 4 in a good way. After all, the showdown between the protagonist and the main villain is what readers look forward to the most.
Q: The idea of Kira's father guiding the air bombs with his cell phone was brilliant.
Sekiya: It seems that was inspired by submarine torpedoes. I looked into it myself, and there are types of torpedoes that automatically track targets and types that are guided by people relying on sonar. It seems this concept was brought into the Stand battle. Regarding Kira's death, Sensei said, "While there are endings where the protagonist beats up the enemy, like in Part 3, I think it's fitting for Kira to die like this."
Q: In the latter half of Part 4, Hayato Kawajiri gained quite the prominent role.
Sekiya: In Sensei's mind, that role was originally supposed to be Koichi's. Originally, Part 4 was planned to be a growth story for Koichi, so that's why Koichi's Echoes grows from ACT1 to ACT2. Alongside the narrative flow of Josuke challenging the "fear in everyday life" of Kira, a murderer who has blended into everyday life, we also planned a flow where Koichi would grow both as a Stand user and as a person. That's why most episodes involved Koichi in some way. However, when we decided to place Hayato close to Kira, the flow shifted to Hayato being the one who uncovers Kira's true identity. With this shift, the story became more focused on Hayato's perspective, which might be why Koichi was reintroduced at the beginning of Part 5.
Q: Killer Queen's third bomb, Bites the Dust, was a Stand ability that blew away time.
Sekiya: Bites the Dust was a Stand that Sensei struggled a lot with. We had the first and second bombs, but we knew that those alone wouldn't be enough for the final fight, so deciding on the third bomb's ability was a challenging process. Sensei's mindset at the time was: "If you want to make something more powerful, it has to involve time," but even if time would be blown away and then reversed, we had difficulties with those rules.
Stands generally have a "if you do this, then this will happen" rule, and we argued about these rules for about three weeks, especially around the time Kira kills Hayato in the bath. During that period, even the usual quick phone calls for checking drafts were filled with Sensei's frequent remarks like, "Hmm... this doesn't quite work..." From there, when we scheduled meetings together, we would become increasingly frustrated at each other as we tried to finalize Part 4. I think we consistently talked on the phone for about three hours at that time. Sensei seemed to have a lot of trouble with Bites the Dust, and I think it caused him a ton of stress.
I'm not sure if I should say this, but around that time, Sensei would occasionally ask, "Should we end JoJo with Part 4?" However, as we got closer to the end of Part 4, Sensei began thinking about doing a Part 5, and I repeatedly responded with, "Absolutely, let's do it!" That just goes to show how challenging it is to come up with Stand ideas and plot developments that will shock readers every week.
Q: Part 5 has a more independent development compared to the rest of the series. Do you think there were any emotional shifts on Sensei?
Sekiya: I think there were. After doing so many Stand battles throughout Parts 3 and 4, and continuing the series for such a long time without any breaks (whether or not to end the JoJo series aside), I believe he had a desire of wanting to have a little break or even a conclusion at the end of Part 4.
Q: Do you know how the concept for Part 5 was developed?
Sekiya: We talked about setting the story in Italy from the beginning. However, the protagonist had to be a descendant of the Joestar family in some way, so that stumped us for a bit. Sensei even had a (possibly joking?) idea of, "Should we make Joseph cheat again?" but both of us concluded with, "That's not going to happen" (laughs).
Q: So, you changed the perspective to make him DIO's child?
Sekiya: Since DIO's body is Jonathan's, he would be part of the Joestar family. In our early meetings, we talked about the fact that he is also the child of the vampire DIO, so we asked questions like "Should we make sunlight a weakness?" or "Should sunlight give him a tingling feeling?" Sensei also likes gags, so there were actually quite a few such ideas. Another point is that Sensei said, "I want a woman to be the main protagonist."
Q: This is for Part 5, right? You don't mean Jolyne from Part 6, but Giorno as a woman?
Sekiya: Around the time he brought it up, Giorno's name hadn't been decided yet. It's not an issue these days, but back then my impression was that a female lead in a shonen manga would have been very tough to sell. During that era of Jump, it simply wasn't the time. Thus, during my meeting with Sensei, we spoke about this and that, and in the end, the protagonist ended up not being a woman. However, Giorno's stand has the ability to create life, right? Women give birth to life, so I think this concept was probably left over from the idea of having a female protagonist.
Q: Giorno is an elegant and somewhat androgynous character. Is the initial idea of having him be a woman related to that?
Sekiya: Giorno's real name, Haruno Shiobana, is also very feminine, right? Sensei may have been thinking of having the story unfold with Giorno being revealed to be a woman. Now that I think about it, he used to joke around with ideas, saying things like: "What about if it was a woman who looked like a man? Wonder if that would work?" (laughs)
Q: Sensei has a rather playful side (laughs).
Sekiya: Yes, he does. When Sensei had an exhibition in Paris in 2003, I went to visit him and I heard that internally he was grateful, but when I saw him he acted rather indifferent on the outside, saying "Oh, you came?" He is surprisingly shy, or tsundere in that way (laughs).
Also, he doesn't seem to dwell much on the past. For instance, when Josuke almost fell from the transmission tower during the fight with the Stand Super Fly, Sensei suggested, "Can't Crazy Diamond's ability bring him back to the tower?" I had to remind him, "No, Sensei, the rule is that Stands don't affect their users." And then he said, "Well, that's the thing..." Eventually, he started saying things like, "Maybe Josuke's determination can do it" (laughs).
He has a tendency to speak directly about what he thinks or feels. He often says things in a straightforward way that others might usually soften. It's not a bad thing and often contributes positively to the work, making it interesting. He doesn't cling to any particular Part either, so when I became his editor, he told me, "Since JoJo is so long, starting from Part 3 is enough to read." Against his instruction, I instead re-read from the first volume. Even though I was only there for a year, it was a very memorable experience.
Q: So the series is quite dense.
Sekiya: Yes, checking the manuscripts was also quite intense. The weekly serialization typically consists of 19 pages, but his manuscripts usually clocked in at about 20 to 21 pages. I had to cut 1 to 2 pages each time, and we would have weekly discussions over the phone about how to fit it into 19 pages. He'd always tell me, "My rhythm is 21 pages." He explained that, "When I get into a comfortable groove and think, 'this is OK,' it usually turns out to be about 21 pages." Sometimes, the manuscript would come in at 19 pages, but those manuscripts seemed a bit drawn out. I think it's about creating the right balance of getting the manuscript to 21 pages, cutting unnecessary parts, and concentrating on showing what needs to be shown to create a stronger impact for every chapter.
Q: You were mainly in charge of Part 4, but were there any words from Sensei that left an impression on you?
Sekiya: I was going to leave as editor after about a year, and when it was time to hand the role over to the next person, Sensei said, "You're leaving already? Isn't that a bit short? I kind of had a feeling it would be like this." It seems that the previous editors, Sasaki and Kaito, were also both in charge for about a year each, and I was no different. I think Sensei, who was just beginning to form a relationship with the editors, always found it hard to switch editors again and again.
Personally, I have grown a lot by being in charge of Araki-sensei. Although Sensei is about 10 years older than me, we worked on equal terms despite the age difference. Even now, Sensei looks very young, and sometimes I think that he's actually younger than me. I feel like he thinks and draws things from the perspective of a young man. That's why he always looks young (laughs) and I think his work is able to adapt to the times.
If he were thinking from the perspective of his actual age, in his 50s, he wouldn't be able to create a story as interesting as JoJolion. In that sense, both Araki-sensei and JoJo are constantly evolving and always feel new. So, I think that's what makes JoJo great. As long as Sensei's passion continues, even if it's not under the JoJo title, brilliant new ideas will continue to be born. That's how I feel.
――関谷さんの担当パートは、どこからでしょうか。
★第4部で
――第4部は、当時の「週刊少年ジャンプ」(以下、WJ) 読者の反応はどうでしたか?
★前任の垣内が担当していたパートの最後あたり、吉良が顔を変えて逃げ切るところでは、もう第4部クライマックスか⁉ と読者も盛り上がっていたと思います。ただ、僕が引き継いだ時は仗助も承太郎も出ない時期でしたから読者の反応が薄くなっていました。もちろんコアな『ジョジョ』ファンはたくさんいたんですが、人気アンケートとかいちばん分かりやすい読者の反応としては、表れにくかった部分もあります。『ジョジョ』に限らず長期連載作品はどれも似た傾向になると思いますよ。荒木先生がさほど気にしなくても、それでもやはり担当編集としては読者の反応は気にする部分ですから、それとなく人気キャラの承太郎を出してほしい話を先生にふっても「承太郎は時間を止めるから誰も勝てないんだよね。ズルいよねー」と却下されたり (笑)。そうこうしているうちにも吉良と仗助が空気弾で戦うエピソードあたりから盛り上がってきて、結果的にいい形で第4部を完結できました。やはり主人公とラスボスの対決は読者がいちばん期待するところです。
――吉良の父親が携帯電話で空気弾を誘導するというアイデアが秀逸でした。
★あれは潜水艦の魚雷がモチーフのようですね。僕も調べてみたんですが魚雷には自動追跡するタイプや、ソナーを頼りに潜水艦が誘導するタイプなどがあって、その構図をスタンド戦に持ちこんだようです。吉良の最期に関しては先生は「第3部みたいに主人公が敵をボコボコにするっていう最期もあるけど、吉良はこういう死に方で良いんだよ」ということは言っていました。
――第4部は後半で川尻早人の活躍も目立ちましたね。
★あれは先生の中では、当初は康一の役割のはずだったんですよ。もともと第4部は康一の成長物語にもする予定で、だから康一のエコーズもACT1、ACT2と成長する設定にしていたんです。吉良という殺人鬼が日常に溶け込んでいるという「日常の中の恐怖」に仗助が挑むという流れの横で、康一がスタンド使いとしても人間としても成長していく流れも敷く予定でした。だから大抵のエピソードに康一も絡んでいる展開になっていたんですが、吉良の身近に早人というキャラクターを置いたら、いちばん近くの早人が吉良の正体を暴いていくという流れに変わっていったんです。そんな感じで途中から早人目線になってしまったので、それもあって第5部の冒頭で康一を出したのではないでしょうか。
――キラークイーンの第3の爆弾であるバイツァ・ダストは、時間を吹き飛ばすというスタンド能力でしたね。
★バイツァ・ダストはかなり先生も悩んでいましたね。第1、第2の爆弾はあったけど、それだけではラスボスとしてキツいというのも分かっていて第3の爆弾をどんな能力にしようか、というのはかなり難産でした。「パワーアップするなら時間に絡めるしかない」というのはもともと先生の考えの中にあったようですが、時間を吹き飛ばして巻き戻るにしても、その約束事には悩みました。スタンドって基本的に「これをしたら、こうなる」という約束事なんですよ。その辺の約束事を、吉良が風呂場で早人を殺す週の前後あたりから3週間くらい、ずっと一緒に考えていましたね。その頃はチェック用のネームのやりとりの電話も普段ならすぐ終わっていたのに、先生の「うーん…これだとちょっとさぁ…」という発言が多かった記憶があります。そこからもう一度打ち合わせが始まって、展開がうまくまとまらずにお互いにイライラしながら話していたこともありましたね。その時は電話で3時間くらいやりとりしていたかな? バイツァ・ダストの使い方は先生もかなり苦悩した部分で、そういった点も含めて先生はかなりしんどかったようです。これは言っちゃっていいか分からないんですけどちょうどその頃、「『ジョジョ』はもう第4部で終わりにしようか?」といった旨の発言もありました。ただ、第4部のラストに向かうにつれて「第5部もやろうか」という話が先生からも出てくるようになってきたので、こっちも「絶対やりましょうよ!」と。それだけ毎週、スタンドのアイデアや読者を驚かすような展開を考えるのは大変だということですね。
――第5部はシリーズの中でも独立した展開になっていますが、先生のそういった心の動きもあるんでしょうか?
★あったのではないでしょうか。第3部、第4部とスタンドバトルをやって、しかもお休みもなく長く続けていたので『ジョジョ』のシリーズを終えるかどうかは別にして、「第4部でちょっと一区切りつけたい」という気持ちになってもいたんだと思います。
――第5部の構想は、どういった流れで形作られていったか分かりますか?
★イタリアを舞台にしたい、というのは最初から話がありました。ただ、主人公はどんな形であれジョースター家の血を引いていないといけなかったので、そこは先生も迷ってましたね。「ジョセフにまた浮気させるか」みたいなアイデア (冗談?) もちょっと出たんですが、先生も僕もお互いに「それはないよね」という結論で (笑)。
――それで視点を変えてDIOの子供という形に?
★DIOの肉体はジョナサンなのでジョースター家の血筋になりますから。初期の打ち合わせでは吸血鬼DIOの子供でもあるので「日差しは苦手にしようか?」「太陽の光を浴びるとチクチクするとか」なんて話もありましたね。先生はギャグも好きなので、そういう類の設定も意外とありますよ。それともうひとつ、先生からは「主人公を女性にしたい」という話がありました。
――第5部ですよね? 第6部の徐倫ではなく、ジョルノが女性?
★ジョルノっていう名前もまだ全然決まっていなかった時期なんですが。今だったら違いますが、少年誌の漫画で女性を主人公にするのは、辛いのではないかという印象が僕にはありました。当時のWJはまだ女性主人公という時代ではなかったんですね。そこは先生とも打ち合わせで色々話していく中で最終的には主人公は女性にはならなかったんですが、ジョルノのスタンドは「生命を生み出す」という能力ですよね。生命 (子供) を産めるのは女性だけですから、そこは「女性が主人公」という案の名残なのかなと思います。
――ジョルノは華奢で中性的なキャラクターですが、初期案で女性だったことも関係しているのかもしれませんね。
★ジョルノの本名も「汐華初流乃 (しおばなはるの)」という女性的な名前でしょ? もしかしたら「実は女性でした」という展開も考えていたのかもしれないですね。…そういえば「男みたいに見える女とかはどうかな? ダメかな?」とか、そんなギャグみたいなアイデアも先生は言ってましたね (笑)。
――先生は割とお茶目なところもありますね (笑)。
★そうですね。先生は2003年にパリで個展を開かれたんですが、そこにお邪魔した時も内心は「ありがとう!」だったらしいんですが、先生は「なんだ、来たの?」くらいに素っ気ない感じで、意外とそういうところは恥ずかしがり屋というかツンデレというか (笑)。あと、あまり過去に執着しなかったりしますね。スーパーフライという鉄塔のスタンドとの戦いで仗助が鉄塔から落ちそうになった時も「クレイジー・ダイヤモンドの能力で鉄塔に戻れないかなぁ?」と自分から言い出して。「いや先生、スタンドは自分には効果がないのがルールでは…」「そこをさぁ…」みたいなやりとりがあったり、そのうちに「仗助の気合いでなんとかなるんじゃないかな」ということを言い出したり (笑)。割と思ったこと、感じたことをスッと口に出して言うところがありますね。普通であればオブラートに包んだりするようなことも感覚的にスッと話す。それが悪いことではなくて良い方向に出ている部分が多いから作品的にも面白いんだと思います。ある部分には固執しないところもあって、担当になった時も先生から「『ジョジョ』は長いからさ、読むのは第3部からで十分だよ」という声をかけてもらったり。いや、もちろん担当するに当たって第1巻から読み直してはいたのですが。わずか1年という期間ですが、かなり印象に残る担当作品でした。
――それだけ密度が濃かったということですね。
★ネームのチェックも濃かったですね。毎週の連載は基本的に19ページなんですが、ネームはたいてい20~21ページで上がってくるんです。1~2ページ分を削らなければいけなくて、先生と電話でどこをどうすれば19ページに収まるかの打ち合わせを毎週やっていました。これは先生自身が言っていたことなんですが、「自分のリズムが21ページ」なんだそうです。「気持ちよくネームを割って、これでOKだ! って思って数えるとだいたい21ページ」だと。たまにネームが19ページであがる時もあったんですが、そういう時はちょっと間延びしている印象もあったかもしれません。やはり21ページでネームを割って要らない部分をカットして、見せるところはしっかり見せて凝縮していくことで連載1本分のメリハリがつくのだろう、と思っています。
――第4部を中心に担当されていたわけですが、印象深い先生の言葉などありましたか?
★僕は1年くらいで担当を離れることになったんですが、次の担当に替わりますって時に先生から「もう替わっちゃうの? 短くない? なんかそんな気もしてたんだよな〜」というお話はありました。前任の佐々木も垣内も1年くらいだったはずで、私もそうですが、先生としては担当との関係がやっと築けた頃にまた交替というのが辛かったのだと思います。僕自身も荒木先生の担当になって成長させてもらった部分がめちゃめちゃ大きい。先生のほうが僕より10歳ほど年上なんですが、年齢は離れていても対等という感じでやらせていただけました。今でもそうですが先生の感覚は非常に若くて、もしかして自分より年下なんじゃないかと錯覚する時もあるくらい。少年というか青年というか、その年代の感覚のままで物事を考えて描いているという感じがします。だからずっと見た目も若いままだし (笑)、作品が時代に対応できるんだと思いますね。50代という先生の実際の年齢で物事を考えていたら『ジョジョリオン』のような作品は面白く描けないでしょうし、そういった意味で荒木先生も『ジョジョ』も常に進化していて、日々新しい。だから『ジョジョ』は良いんじゃないのかなと思います。先生の気持ちが続く限り、『ジョジョ』というタイトルなのかどうか分からないけど新しいものが生まれていく。そんな気がしています。
Q: Part 6 had the first female protagonist. Was this Araki-sensei's idea?
Azuma: That's right. As a shonen magazine editor, I politely asked him to make the protagonist a boy, but he refused in 3 seconds (laughs). The readers of Weekly Shonen Jump wouldn't accept a female lead, which is why I wanted him to change it, but he just replied, "That's exactly why we're doing it".
Looking back at the series's popularity at the time, I still believe that a male protagonist would have been better. However, considering the long history of the JoJo series, I also think that it was overwhelmingly beneficial that the Part 6 lead was female. I get the impression that Araki-sensei is the type of person who won't repeat the same thing twice. He is the type of artist who constantly takes on new challenges, so maybe he instinctively knew he'd lose the motivation to draw if he chose a male protagonist just for notoriety's sake.
It was around then that strong female leads had also begun appearing in films, so perhaps he thought the time was right. If he really cared about gaining popularity, he could have just made the protagonist something like a "miniature" version of Jotaro from Part 3. He wouldn't do that though, he's the type of artist who has to continue fighting.
Q: From an editor's point of view, what type of artist did Araki-sensei seem like at the time?
Azuma: He could construct both the characters and the story firmly in his head and always met deadlines, making him very easy to work with and highly valued by the editorial department. I suppose I was chosen to be Araki-sensei's editor because the higher-ups thought that our hobbies were similar, rather than my suitability as a manga editor. Much like Araki-sensei, I also love music and films, and I know pretty much all of the music that he listens to. I think the editorial department considered it important that Araki-sensei was able to work comfortably. I had the privilege of working for him for two-and-a-half years, but at that point only about 5 of my ideas were used (laughs).
――第5部から担当されていますが、先生からテーマ的なことを聞いたことはありますか?
★「第5部は集団劇をやりたい」という話は聞いていました。「主人公はジョルノではあるけれど、チームの誰もが主人公でもあるという形にしたい」ということも言っていましたね。第5部に限らず主要キャラが何人も死ぬ展開が多いですが、そこは先生の中で「リアルな世界で描きたい」「誰も死なないなんて有り得ない」といった気持ちがあったんだろうと思います。人気を取るために誰かを死なせて盛り上げるといったいやらしい発想ではなくて、ギリギリの命がけの戦いをやっているんだから誰かが死ぬのは先生の中では必然だったんでしょうね。
――第5部の「黄金の風」、第6部の「ストーンオーシャン」といった各部のサブタイトルは東さんの担当時代に付けられたものですね。
★それは次の第6部のスタートと関係しています。『ジョジョ』は長期連載で「週刊少年ジャンプ」(以下、WJ) の看板作品だし、雑誌としても必要ということで第5部が終わっても連載は続けていただきたい、というのが編集部の考えだったんですが、一方で連載が長すぎて新規読者が入りづらいという問題点もあったんです。そこで第5部の完結が見えた段階で、編集部から「主人公の名前はジョジョでいいが、『ジョジョの奇妙な冒険』というタイトルは変えられないか」という相談をしています。タイトルを新しくすることで新連載という体裁をとり、今まで読むことを敬遠していた若い読者を取り込んでいこうという考えからですね。第4部とか第5部というと、どうしても今まで読んでいなかった人にはハードルが高いと思われていたみたいなので。ただ、荒木先生としては「どこまで行っても『ジョジョ』なんだから、そういう小手先の対応はどうなの?」というお考えで、たしかにそれももっともなんで、それで「ストーンオーシャン」というサブタイトルを考えてもらって、『ジョジョの奇妙な冒険』と並べて入れましょうという形に落ち着いたんです。だから第6部の最初の頃の連載扉では「ストーンオーシャン」というタイトルも結構大きく出ているはずですよ。で、タイトルをそうしようと決まった頃に先生から「はい」と紙を渡されて「そしたら第1部から第5部のタイトルもいるよね? 考えたから」って (笑)。だから各部のサブタイトルは第6部がきっかけになってますね。それと第6部の時にもうひとつ編集部からお願いしたことがあって、それは「十分な準備期間を用意するので、新作としてゼロからスタートしてほしい」というものでした。これも新規読者の開拓を狙ってのことで、だから第6部の連載開始は第5部終了から半年後でしたし、「ストーンオーシャン」を読むと分かるんですけど「スタンドとは何か」といった基礎的なところから丁寧に説明しつつ展開しているんですよ。
――「ストーンオーシャン」では取材旅行にも行かれたんですよね。
★第6部スタート前の準備期間中だったので1999年の秋頃だったと思います。アメリカのフロリダを中心に一週間くらいだったかな、行ってきました。その時のガイドさんのご家族が偶然にも警察関係の方で、そのつてで刑務所の内部を特別に見せてもらえたりして、すごくレアな体験をさせてもらえました。あれは本当にラッキーでしたね。そういえば刑務所の内部を見ている時、途中で先生の気分が悪くなったりしたこともありました。感受性が豊かな人なので、自分が閉じこめられたら、とか色々考えちゃったのかもしれないですね。
――第6部はシリーズ初の女性主人公ですが、このアイデアは先生から?
★そうです。少年漫画誌の編集者として僕は「男の子にしてください」ってお願いしたんだけど3秒で却下されました (笑)。WJでは女性が主人公だと受けないというのがあったので男性にしてもらいたかったんだけど、先生は「だからやるんだ」と (笑)。ただ、思えばその時の人気だけで考えたら僕は今でも男性主人公が良かったという意見ですが (笑)、『ジョジョ』の長い歴史を考えると第6部を女性主人公にしたことはトータルとして圧倒的に良かったと思います。というのも荒木先生は多分、同じことを2回できないタイプだと思うんですよ。常に挑戦していくタイプの作家さんなので、「人気を取るために男性主人公にしたら作品を描くモチベーションは保てないだろう」というのが本能的に分かっていたのかもしれませんね。当時は映画でも「強い女主人公」というのがけっこう出てきていましたし、そろそろ挑戦しても良いんじゃないか? みたいなことも考えられて敢えて女性主人公にしたのかもしれません。普通に人気を取ることだけを考えるのなら第3部の承太郎のミニチュアみたいな主人公にして、亜流をやっていればいいわけですから。でもそういうことはしたくないし、常に戦い続けないといけないタイプの作家さんなんでしょうね。
――編集者から見て、当時の荒木先生はどんな作家に見えましたか?
★キャラクターもストーリーも自分の中でしっかり組み立てるタイプで、締切も完璧に守るという非常に仕事がやりやすい作家さんでしたし、編集部の中でもそういう評価が高い人でした。なので僕が担当に選ばれたのも漫画編集者の適性というよりは、趣味的な部分で先生と話が合うんじゃないかと上の人が考えたからじゃないですかね。僕も音楽好き、映画好きですし、先生の聴いている音楽もだいたい分かりますから。先生に気持ちよく仕事をしていただければ、という編集部の考えがあったんだと思います。実際、2年半担当させていただいて、僕の出したアイデアって、5個くらいしか採用されていませんよ (笑)。
――先生は、どんな人柄でしょうか。
★非常にきっちりした人ですね。プロ意識が高くて、常に仕事最優先で全力投球。最高のレベルで仕事ができるように環境作りも含めてきっちりとされています。同時にオンとオフの分け方もきっちりしていて、休む時は全力で休みます (笑)。僕が担当している時は合併号の休みが年3回、年末年始とGWとお盆にあるんですが、毎回イタリアに旅行されていた印象ですね。プライヴェートと仕事をきっちり分けるタイプで、当時は主に漫画業界以外の方と遊んでいた感じですかね。なので、荒木先生がWJの新年会に出席される時なんかは大変でしたよ。WJの作家さんにも荒木先生ファンはいっぱいいたので、囲まれちゃって。連載作家さんでも荒木先生に会える機会は滅多になかったので、「今年は荒木先生が新年会に来るらしい!」みたいな感じになって。途中で帰ろうとする荒木先生を、まだ話せていない作家さんがいるから引き留めてくれ、って副編集長に頼まれたのを憶えています (笑)。
――割とご自分の中でこうするっていう、ルールとか決めるタイプですか?
★そうですね。ルールというか、決めごとというか、ご自分で決めて、それをきっちり守る方でしたね。仕事に向き合う上での決めごともいっぱいあったと思いますが、生活全般にも色々ありましたよ。当時のもので印象深かったのは、「新宿以外には行かない」っていう決めごとでしたね。これは、買い物とかたいていのことは新宿の伊勢丹界隈でまかなえるので、基本新宿以外には出かけたくない、それ以外の街とかには行かないことにしている、というものだったんですが、当時先生は毎週金曜日は映画館に行く日と決めていたんですね。ところが観たい映画が例えば渋谷の単館ロードショーだったりすると、「観たい! でも渋谷だから行けない」って、ものすごく、本当に真剣に悩む (笑)。他人からすれば行けばいいじゃないですか、ということかもしれないけど、決めちゃった以上は基本的に曲げない人でした。ひとつをないがしろにすると他の部分も崩れていくというのが無意識にあったのかもしれないですね。「常に最高の作品を作る」とか「締切は絶対に守る」とか、本人は当たり前のことと考えていると思うんですが、常に自分を律する心があって、それがそういう自分ルールみたいな決めごとに繋がっていたんじゃないかと思います。とはいえ、WJの新年会の場所が銀座とか青山だったりすると、真剣に悩んでいたのはおかしかったですね (笑)。「イタリアより近いじゃないですか?」って言ったら、「銀座はイタリアより遠いよ!」って返された時は絶句しました (笑)。もちろん時代や年齢に応じてルール改正もしていると思うんで、今は大丈夫だと思いますが…。
――東さんが担当していた頃に先生の2冊目の画集「JOJO A-GO!GO!」が発売されています。
★第1部から数えて10年近くが経っていて、初期からのコアなファンの年齢層が20歳オーバーと高かったのは分かっていたので、『ジョジョ』に関しては値段は高くてもちゃんとしたものを作れば受け入れてもらえるはずだという意識がありました。逆に言うと、高くてもいいからちゃんとしたものを作らないと見向きもされないとも思っていました。当時のWJでは値段が高くなる画集でも1800円くらいが上限、子供が買える値段じゃないとダメという常識があったんですが、敢えて定価6800円という豪華ボックスの「JOJO A-GO!GO!」を企画しました。当然、上司にも企画書を回していますが、上を説得するのに苦労をしたかというとそんなこともなく「まぁ、そうだよね」という感じで。つまり僕だけじゃなく編集部の上も同じ認識だったんですよね。まぁ、美術書みたいな本を作りたいっていう僕の個人的な願望もあって、それは『ジョジョ』じゃないと出来ないだろー、って思ってたんですけど (笑)。
――「JOJO A-GO!GO!」の当時からアート性のある作家さんだと認識されていた?
★それはある程度は感じてましたけど、まさか今のようにGUCCIとコラボしたり、美術館で展覧会やって、「美術手帖」に特集されたりとか、そこまではさすがに想像すら出来なかったです。すいません (笑)。まあ当時はWJという超メジャーなところで独自の世界をひとりで歩む孤高の漫画家というイメージでしたね。熱狂的なファンがいて、作家陣の中でも独特の地位を築いていて、メインストリームとは別の意味での看板作家という感じでした。作家としてある種のキャラも立っていたので圧倒的な存在感はありましたし、それだけにさっきも触れましたが若い新人作家の中には荒木先生を「神様」と言う人も多かったですね。
――当時の打ち合わせは、どんなスタイルだったんでしょうか。
★昔も今も変わっていないと思いますが、まず雑談でした。映画の話とか、社会で話題になっている事件があれば犯人がどういう人物なのかを話したりとか。それがひと通り終わって、そろそろ打ち合わせしましょうかという流れになる感じです。先生がおもむろにスケッチブックを開いて先週までの流れのメモを入れて、そこから漫画の打ち合わせという感じでした。それと実はこの打ち合わせ用のスケッチブックの他にノートが1冊あって、先生は時々ノートを「ん~…」って考えながらチラチラッと見ることもありましたね。それこそポーカーで、自分のカードをコソ~ッとこうやって見る感じ? (笑) 多分、あのノートには先生が事前に自分で考えた様々な展開案やネタが書いてあるはずです。僕もその中身は見たことがないんですが。
――そのノートは気になりますね (笑)。
★で、打ち合わせの始めに、今週のテーマを決めるんですね。例えば、「今週は敵のすごさを見せる回だ」とか。大枠のテーマを決めて、そこから具体的にどんなアイデアがあるのかを一緒に考えるんです。例えば「敵のすごさを見せるために、ブチャラティが攻撃される。では具体的にどんな攻撃なんだ?」みたいに。まあ実際は僕が色々と愚にもつかないことを言って、「それは違うだろー」とか、「ありきたりじゃない?」みたいなことを言われて、そのうちに先生のアイデアが固まってくる、っていうパターンでしたけど。荒木先生の漫画のセオリーとして、「毎週1話につきひとつのアイデアを入れればいい」というのがあって、欲張ってふたつもみっつもアイデアを入れるとページが足りないし、収拾がつかなくなる。なので、「今週のネタをひとつ考えよう」、という作業でしたね。他にも色々教えていただきましたね。例えば、「少年漫画の主人公は悩んじゃダメだ」というのもありました。これは主人公が戦うにあたって、「どうして僕が戦わなきゃいけないの?」とか、うじうじ考えさせたら絶対ダメ。主人公が悩んでいいのは「強い敵をどうやって倒すか」という時だけだ、っていうルールなんですが、シンプルなんですけど荒木先生に言われると非常に説得力があって、若い漫画家さんの打ち合わせの時とかに役立たせてもらいましたね。
――「敵をどう倒すか」に集中するのは少年漫画の王道ですね。
★荒木作品は完全に王道なんですよ。もともとの根っこはそこでぶれていないんですが他の作家さんとは違ったセンスを持っているから、ああいう作風になるんです。
――でも、そこが『ジョジョ』の大きな魅力だと感じます。
★そうですね。よく「文は人なり」って言って、その人の書く文章には人柄が出てくる、みたいに言われますが、荒木先生を見ていると、「漫画は人なり」って思いますね。正直『ジョジョ』の登場人物っていうのは、荒木先生自身ですからね。『ジョジョ』の主人公たちもこの世に生を受けて、己の為すところを為す、という感じですが、荒木先生も漫画家として為すべきところを為す、という感じで、傍から見るとストイックなまでに作品に身を捧げているのは、すごいなと思いますね。まあ先生に言うと、そんなの当たり前でしょ? って怒られそうですけど… (笑)。
Q: Part 7 takes place in a parallel world from the rest of JoJo up to that point. What were Araki-sensei's thoughts on this?
Shima: From his point of view, "it's alright if it's not connected to Part 6, right?" On the topic of Part 6, he also said, "That's just one of the many Stone Oceans." By the end of Part 6, he had told me about his plans for Part 7, but only in vague terms like, "The next part is about the steel ball." So at first I had no idea what he was talking about (laughs).
――担当されたのはどこからどこまでですか?
★第6部の途中、単行本でいうと第70巻のウエストウッドのあたりからです。第7部は先生と一緒にアメリカに取材旅行に行って第1話を入稿した頃だと思いますので、期間的には3年間くらいですね。
――取材に行かれたのはいつ頃?
★2003年7月頃ですね。舞台を北米にすることは先生の中で決まっていたので、カリフォルニア州のロサンゼルスからサンディエゴ、アリゾナ州のグランドキャニオンなどを一週間くらいで回ってきました。そういえばその旅の道中でのエピソードなんですけど、グランドキャニオンで先生が服が汚れるのも構わず地面に這うようにして植物を撮っていたんですね。ちょっと感動して「僕も撮りましょうか?」と話しかけたら一瞥もくれずに「撮りたきゃあ、勝手に撮れば」と。この佇まいは「露伴」かと思いゾクゾクしましたね。
――コミックス第18巻のコメントにも「お母さんに怒られた」と書いていますね (笑)。
★もうひとつ僕は高所が苦手でグランドキャニオンでは実際生きた心地がしなかったのですが、先生はあえてギリギリの崖っぷちまで行って「全然怖くないよ、こっち来たら?」とニコニコしながら手招きするという…そんなチャーミングなところもあったりしますね。先生の取材スタイルなんですが、とにかく行く場所行く場所で徹底的に風景なら360度全部、建物ならドアから壁紙・調度品に至るまで触れるもの全てを撮影していく感じでした。ですから一ゕ所の滞在時間も相当なものでした。食事も「アメリカには好きな食いもんないからさぁ、バーガーキングでいいんだよね」とあくまで取材優先でしたね。
――第6部の途中から担当とのことですが、作品のテーマ的なことはお話をされましたか?
★先生から直接お話をいただくことはありませんでしたが、打ち合わせを重ねる中で「人間の限界点」を突き詰めたのが第6部なのかなと考えています。ラストに向けての徐倫たちとプッチ神父の戦いも肉体と精神両方を極めたバトルじゃないですか。「限界を超えて強くなっていく」というのが1990年代のWJの王道だとすれば、それを先生の解釈で描いたのが第6部ではないかと。言い方を変えると「運命を乗り越える」という『ジョジョ』ルールの最大進化形ですね。そんな印象を持っていましたので「ここが集大成なのかな。もしかしたら、ここで『ジョジョ』は区切りがつくのかな」とも考えた時期もありましたね。荒木先生担当なら誰もが思うことですが、WJ連載陣の中でも屈指のハイテンションを維持しているのが『ジョジョ』という作品ですので何とか未読の読者にも伝えたくて毎号のアオリにも気合を入れました。
――連載当時、アオリの疾走感がファンの間で話題になっていました。「ザ・ニュー神父」や「NO断念!!」などのアオリは今もファンに語り継がれています。
★たしか先生から原稿をいただいて「神父、かなり雰囲気変わりましたね」と話しましたら、「最新型神父ですよ」と。憶えてらっしゃらないと思いますが (笑)。僕が担当時のアオリは割と荒木先生のおっしゃる言葉にインスパイアされていましたので、原稿をチェックする段階でほぼ決まっていました。
――ベタな質問ですが、好きなキャラクターは?
★担当当時、徐倫側のキャラクターはみんな思い入れがありましたけど、改めて思い返すとプッチ神父ですね。第6部の主人公はプッチ神父だったのだなぁと思います。DIOの意志を継いだとはいえ、ここまで純粋に自身の願望を貫く敵役も珍しいのではないでしょうか。あと、何故かプッチ神父の台詞だけは荒木先生ご自身の声で伝わってくるんです。『安っぽい感情で動いてるんじゃあないッ!』など身の引き締まる思いがします。
――プッチ神父のセリフを読めば、先生のダークな一面が見えてくるかもしれませんね。
★先生のお言葉なのですが、「ダークな部分とコミカルな部分に境界線はない」とよくおっしゃってました。恐怖と笑いが相互に転化しあうのも『ジョジョ』の魅力のひとつだと思いますが、第6部では敵側のキャラクターそれぞれに人間的な深さをあまり描く必要がなかった分、スタンドにより娯楽要素が盛り込んであって、担当という立場抜きで毎回楽しんでいました。
――第7部『スティール・ボール・ラン』はWJでの連載スタイルも毎号30ページ前後を10週前後掲載し、先生が描きためてから再び掲載という変則的なスタイルでしたね。
★あのスタイルになったのは先生から「毎週の連載もできないことはないけど、やっぱまずいと思うんだよね」というお話を頂いたからです。将来を見据えて「ここで色々と削ったらまずいんじゃないか」という気持ちを持たれたんじゃないでしょうか。
――タイトルも『ジョジョの奇妙な冒険』が外れて『スティール・ボール・ラン』のみとなっています。
★タイトルの件は、第6部開始時と同じく編集部からの要望だったはずです。『ジョジョ』ではない新しい作品を作ってほしいという意図があってのことでした。
――第7部はそれまでの『ジョジョ』のパラレルワールド的な世界なんですが、これについて先生の考えは?
★先生的には「別に第6部までと繋がってなくてもいいんじゃない?」という話でした。第6部についても「あれはいくつもあるストーンオーシャンの中のひとつなんだよね」と。第6部の終わり頃には第7部の構想も先生から伺っていたんですが、端的に「次は鉄球なんだよね」みたいな感じでしかおっしゃらないので、最初はさっぱり分からなかったですね (笑)。ただ先生の中では「舞台はアメリカ」「ゴールを目指す展開」「取材旅行が必要」といったことは決められてましたね。
――先生は順位は気にしないという話を歴代担当さんが話されていますが、第6部や第7部の当時も同じですか?
★まったく気にされませんでした。第6部は3年くらい連載が続いたんですがWJの連載会議で「終わりも検討しよう」といった話は出ていなかったですね。
――当時の打ち合わせは、どういったスタイルだったんですか?
★僕の場合は前の週に見た映画、主にホラーやサスペンス映画ですが先生のアンテナに引っかかりそうな話題を話すところから始めていました。そうした雑談から先生の思考時間に入りまして、途中、先生の頭の中で生まれた疑問に適宜対応していくというスタイルですね。「『ピノキオ』って著作権どうなってんだっけ?」とかですね。しばらくしておもむろに「できた!」という呟きから愛用スケッチブックを広げると翌週のプロットを流れるように書き込まれていく感じでしょうか。そこで、「今回はどんな話に?」「う〜ん、教えたくないな〜知りたい?」「いえいえ、そこを何とか…」というやり取りがあったりします (笑)。
――ああ、そこは露伴っぽいですね…。編集者から見て、荒木先生はどんなタイプの作家だと感じていますか?
★描きたいテーマがあらかじめ決まっていて、決してブレないタイプの作家ですね。頑固とは違って、頑強な骨組みが既にあるイメージです。そこに新しい映画・本・音楽あるいは僕らとの雑談の中から次々と情報を取捨選択して娯楽要素を肉付けしていく。時流に乗った新しい要素を貪欲に吸い上げていく印象がありますね。
――血ではなく題材を吸う (笑)。
★これは思い込みも入っているのですが、先生レベルの作家は無自覚に自分の前世とか歴史をわかっているんじゃないかなと感じることがあるんです。国が違ったり時代が変わっても限られた資料で全体を把握したり、ご自身の解釈で描けたりするのですから。繰り返しになりますが、先生の中で描くべきことが何かを自覚していると思います。
――描く内容はもう決まっていて、それを出力しているだけというイメージ?
★出力するだけじゃつまらないから、ひと捻りも加えてみて…という感じです。漫画雑誌のひとつの頂点であるWJで、何年にもわたって生き残って描き続けてきた作家の方々を見ると本当にそう思います。
――2010年頃からは大きな『ジョジョ』ムーブメントが来ましたね。
★荒木先生は、ご自身とご家族も周囲を引き寄せる「引力」を持ってらっしゃると感じます。2003年4月にパリで個展を開かれたのですがその折奥様が「いつか欧州のブランドと『ジョジョ』がコラボできれば面白いわよね」とおっしゃっていました。その後2009年のルーヴル美術館、2011年のGUCCIとのコラボレーション企画と結果的に『ジョジョ』25周年&デビュー30周年を迎えるタイミングで実現したことを考えますと、やはり偶然ではなく必然を感じてしまいますね。
――『スティール・ボール・ラン』の冒頭から担当されていますが、「週刊少年ジャンプ」(以下、WJ) の連載は変則的なスタイルでしたね。
★そうですね。短期集中というか、10週載せたらしばらく休んで描きたまったら掲載して…、という変則的な連載スタイルでした。なので話数で言えば僕が実際に担当したのは20週分とかそれくらいで、途中で「ウルトラジャンプ」(以下、UJ) に移籍したので期間で言っても1年間くらいと短いですね。
――不定期連載というスタイルは荒木先生からの提案という話ですが。
★先生からの要望だったと聞いています。『スティール・ボール・ラン』の立ち上げに関しては実は前任の嶋がすでにある程度の打ち合わせもすませていて、先生も原稿に入っている頃でした。その時点で、嶋が他誌に異動となったので僕が担当することになったんです。僕の担当した頃は、連載スタイルとか移籍とかの件も含めて、歴代担当の中ではかなり特殊な時期を過ごしてきたと思います。
――WJからUJへの移籍の経緯を知りたいのですが。
★WJは小学生をメインとした少年読者がターゲットの雑誌です。『ジョジョ』はWJの看板作品のひとつだし、単行本も安定した人気で数も出ていたんですが、連載が長くなりファンの年齢層が上がっているのかもといった空気が、編集部でも第6部の途中あたりからありました。それで第6部が終わったあとあたりで、編集部の上のほうと荒木先生とで話し合いをしたと聞いています。その時には先生から「描きためる」という案も出ていたので、編集部から「描きためスタイルで掲載しましょう」「『ジョジョ』のタイトルは外して、新しい作品として描いてほしい」という話になり、なのでタイトルは『ジョジョ』ではないし、キャラの名前はジョジョだけど過去のシリーズとも繋がっているような、いないような、そんな形で新作として始まってますね。ただ、その前から先生としても段階を踏んでWJではない何処かに移籍するということを、ずっと考えていたと思います。そのあと、先生側から「UJに行こうかと思っています」というお話が出たので、僕はそれを編集部に持ち帰って、上司にも相談して…、という流れでした。
――持ち帰って編集部の反応は?
★「もう少しWJでやってもらえないか」という話を僕の上司が先生にしたようですが結局、荒木先生のお気持ちが「WJはそろそろかな」ということでしたので、先生がそうおっしゃっているのなら…という感じでした。当時は月刊誌でいうとUJの他に「月刊少年ジャンプ」もあったんですが、先生はUJの井藤とのパイプがあったので移籍先にUJを希望されたんだと思います。
――『スティール・ボール・ラン』というか『ジョジョ』は、WJの看板のひとつでした。それがなくなったことで、雑誌的に何かしら影響はあったのではないでしょうか。
★今でもそうなんですが長い連載作品が終わると、やはり読者のモチベーションが落ちるんですよ。でも、そこで新しい人気作品を立ち上げて、落ちたところをまた吸収して底上げしていくという感じなんです。もちろん長期連載作がなくなることで離れていく読者もたくさんいるはずなので売り上げ的にも影響がなかったわけではない。でも荒木作品はUJという受け皿も決まっていたわけで、卒業という言い方が僕はいちばんしっくりきていますね。
――作品の話に戻ります。先生からは『スティール・ボール・ラン』をどういった展開にしたい、といった構想を聞いていましたか?
★ラスボスである大統領については、当時はまったく話はしていませんでした。もともと先の展開は決め込まない作家さんでもありますので、当時はとにかく「純粋にレースの話だ」と言っていました。遺体の話も僕が担当している時に出た記憶はなく、大統領もUJ掲載時から出たキャラクターなので、やはり走りながら物語を作っていったという形のはずです。
――『スティール・ボール・ラン』や荒木先生について、特に印象深いエピソードはありますか?
★どの作家さんもそうですが、担当が替わってしまうのは気持ち良くないことだと思うんですよ。先生もそういう部分があったのか、最初の顔合わせで「嶋さんとは一緒にアメリカ取材にも行ったんだけどなあ」といったことをポロッとおっしゃって、あらためて「腹を決めてやらねば!」と。それで、ひとりでアメリカへ取材旅行に行きました。先生と嶋が辿ったルートを、僕がまたひとりで辿るという (笑)。
――それが担当になって最初の仕事?
★そうです。先生が辿ったルートを再び辿ることで共通言語ができるわけで、これは打ち合わせの時もすごく役にたちました。「あの山の形がさぁ」と言われた時に「ああ、あれですね」と。それがあるかないかで、漫画の背景の見え方が違ってくる。砂漠にも行きまして、先生が行かれた時は真夏だったのでものすごく暑かったそうですが僕が行ったのは12月の頭なので寒くて閑散としてまして…。グランドキャニオンのロッジにひとりでポツンと泊まったという、そんな思い出が (笑)。
――荒木先生の才能はどういった部分だと感じていますか?
★唯一無二の作家さんという点ですね。ネームや打ち合わせのスタイルといった点もそうですが、自分のやり方というものがちゃんとあって、それが他の作家さんとは違う独特なものがある。作家さんは皆さん独特といえばそうなんですが、荒木先生は特にそういう自分のスタイルというものがある方ですね。僕の知る限り荒木先生と似たタイプの作家さんはいないし、だいたいあれだけちゃんとスケジュールを管理できている人は僕の知っている限り『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の秋本治先生以外にはいないです。
――担当を離れてからのお付き合いというのは?
★荒木先生は暑いのが苦手なので夏は毎年、地方で仕事をされるんです。オフの日などはそこに招いてもらっています、歴代担当編集が集まるという濃いイベントなんですが (笑)。そこで他愛もない話をしたり、一緒に川に遊びに行ったりアトラクションみたいなもので遊んだり。男ばっかりですけど (笑)。
――そこで漫画の話は?
★まったくしないですね。荒木先生が漫画の話をするのは僕の時は打ち合わせの時だけでした。しかも他の漫画の話も全然しなくて、本当に『ジョジョ』の話だけでした。それも、その時に描いている『ジョジョ』の「次回の展開をどうするか」という点だけで、逆にラスボスの構想とかクライマックスの展開だとかも話しませんでしたし、過去のキャラクターについてもまったく話さなかったです。
――瓶子さんは、WJの編集者として荒木先生と作品の変遷を見ていた方になります。
★僕がWJに配属されたのが第3部のクライマックス、承太郎とDIOの決着の頃だったと思います。第3部は異色ではあるけれど少年漫画の王道だと思うんですが、第4部の頃になると荒木先生の作家としての色がより強く出たというか、作家として成長した感じがありました。この頃からカリスマ的な人気も出始めて、編集部の中でも「『ジョジョ』って他とは違うね」「特別な作品だね」という空気が強くなっていましたね。僕が『スティール・ボール・ラン』を担当した頃までは、僕の中でもマニア色が強くてファンの年齢層も高い作家さんという印象だったんですが、2010年頃から巻き起こった一連の『ジョジョ』ムーブメントでは若い女性層やライト層も取り込んでいて、もう「いったい何が起きているんだッ⁉」というくらい驚いています。長い作品には調子が良い時期もあれば、悪くなってしまう時期もあって、ビジネス的にも長期タイトルを再活性化させる戦略が必要だと思うんですが、そういう意味では『ジョジョ』は常に良いお客さんを持っているし、獲得したケースだと感じています。
Q: As a supervisor at the editorial department of Weekly Shonen Jump (hereafter WSJ), how exactly were you involved with Araki?
Saito: I was in charge of Thus Spoke Kishibe Rohan Episode 5: Millionaire Village, a one-shot that was published in WSJ, up to and including the meetings. Even without a serialization, there were still various communications and reports to be made, so I took over that responsibility from the previous supervisor, Mr. Heishi. Millionaire Village started when Mr. Araki asked to draw a one-shot for WSJ, and the theme of a battle of manners surfaced as early as our first meeting.
Q: How did readers react to the one-shot?
Saito: The survey results were very good. Since it was a battle of manners, you didn't need any prior knowledge to read it. Mr. Araki even seemed to have taken the readability of the story into account, so that even younger readers who were unfamiliar with JoJo could accept it as a slightly unusual psychological battle manga.
Q: What was your impression of Millionaire Village during the meetings? That was your first time working as an editor, wasn't it?
Saito: Even after we decided on the theme of a battle of manners, Mr. Araki came up with a lot of ideas for how to develop it, and I also threw in various ideas as we went along. I was a little surprised at how well-structured the story became from beginning to end, compared to those of other writers.
Q: As an active editor at WSJ, it's safe to assume you're in contact with many young manga artists and writers. Do many of them respect JoJo?
Saito: Very many. I think the influence it has on our creators is extraordinary. The appeal of it to young writers is the fact that anyone can easily recognize JoJo at a glance. In terms of its content, it is overwhelmingly sharp, and it has such a unique feel that it feels as though only Mr. Araki could draw it.
As a matter of fact, I re-read the second part of the series the other day, and I found that the amount of ideas for battles in the series was extraordinary, far beyond other works. The fact he did all that in a weekly serialization astonished me. That, and it's so visually interesting. When I became a manga editor, I learned that the design and visual elements of a manga are quite significant. In particular, he's designed more than 130 Stands by this point. Even though they're based on Japanese yōkai and folk art from all over the world, he takes care to separate them in his mind, so that the silhouettes don't overlap.
Q: You could say the same about the human characters.
Saito: Also, I think creators admire him for doing what he wants to without hesitation. He wouldn't say that about himself, though. For example, even when we discussed the idea for the one-shot Millionaire Village, he himself said, "The readers will hate this idea," about five times or so., "The readers won't be satisfied with this idea. He has a sense, even if it's illogical, that, "the readers won't be satisfied if I don't go so far." He doesn't necessarily draw whatever he wants.
When it comes to creators, the re-evaluation of JoJo over the past few years has largely been driven by people who read the series in real time, who became creators and said, "I'm a fan of JoJo," which led their fans to also reach out and say, "Well, I'll give it a shot," or, "JoJo might be in fashion." I believe that's the biggest contributing factor. I also think that by having those creators talk about JoJo, longtime fans became more comfortable with saying they like JoJo. In the past, if you said you were a JoJo fan, people would tend to think you were a maniac. The hunger of those long-time fans must've been enormous. Up until a few years ago, the only JoJo merchandise available to them was the comics and the artbooks, so there was an unbearable hunger for all things JoJo. Now that they're adults, they're part of a generation with money to spend, so I think they're buying up a lot of merchandise to make up for what they lacked until now.
Q: What do you remember most about your relationship with Mr. Araki?
Saito: One time, when I was scheduled for a dinner with Mr. Araki, I got lost and was very nearly late, so I ran into the restaurant. He warned me, "You shouldn't run in restaurants" (haha). He's very conscious of public order and morality. On another note, Millionaire Village has an episode number. When Araki drew Episode 16: At a Confessional, the first episode of Thus Spoke Kishibe Rohan, he decided to call it Episode 16 because he wanted it to have the aura of being part of a spin-off series. However, he didn't seem to regard it as very important, and the second work, Mutsu-kabe Hill, didn't actually have an episode number. I was such a fan of Araki's that when I read the first work, I wrote a letter to him saying, "I want to read the other 15 episodes!" So during the meeting for the third work, Millionaire Village, Araki completely forgot the episode number again (haha), but I asked him to number it Episode 5.
Q: Which JoJo character do you feel best matches Mr. Araki in personality and character?
Saito: People often bring up the character Rohan Kishibe, but in my own opinion, the two don't overlap at all. I thought he most resembled... Yoshikage Kira, maybe? I feel like his philosophy of leading a normal life while refusing to compromise his beliefs is similar to Mr. Araki's. He decided to fight Josuke due to his beliefs, as well, and that fit the impression I had of Mr. Araki. In my head, Kira's lines are voiced by Araki himself (laughs).
Q: As an editor and a fan of Araki's, what's the main appeal to him and his works?
Saito: I apologize if this is a bit personal, but back when I was in high school, I always had Volumes 46 and 53 of JoJo in my bag (laughs). I loved the cover illustration of Volume 46, with Josuke and Kira glaring at each other, and the composition of the art alongside the title of "Crazy Diamond is Unbreakable" was irresistible. Volume 53 is "The Grateful Dead," and it's a wonderful episode, being a locked-room drama on the express train to Florence while also having a lot of action. I would read either of the two comics on my way home from school, so much so that I must have read each one a hundred times or so. If I hadn't come across JoJo in WSJ in my second year of junior high, my life would have been completely different. In that sense, personally, Mr. Araki was like a god to me.
But when I actually met him, I got the impression that he was a normal person, though he was a bit eccentric in some regards. But that's the point, that he's a bit eccentric. For example, his taste in movies is very different from the average viewer. He's a big fan of the movie Dawn of the Dead, directed by George A. Romero. When I asked him what he liked most about it, he said, "I love the part where the survivors barricade themselves inside a shopping mall and help themselves to anything they want." It's a scene that makes you think, "That's it?!" But I feel like he has a sense, or perhaps a talent, that notices things others don't pick up on. I get the impression that he is a very intelligent person, the kind who can analyze why a movie moves him or why he finds it interesting.
――週刊少年ジャンプ (以下、WJ) 編集部での担当という形ですが、具体的にはどういった関わり方でしょうか。
★WJに載った読切の『岸辺露伴は動かない ~エピソード5:富豪村~』は打ち合わせも含めて僕が担当しました。それと連載がなくても諸々の連絡や報告もありますので、それも前担当の瓶子から引き継いでやっています。『富豪村』はもともと荒木先生が「WJで読切を描きたい」と希望されたところから立ち上がっていて、最初の打ち合わせの時にはもうマナー対決というテーマは出ていましたね。
――読切の読者の評判はどうでしたか?
★アンケート結果はめちゃくちゃ良かったです。マナー対決だったので予備知識が無くても入れる内容ですし先生も読みやすさを意識されていたようなので、『ジョジョ』を知らない低年齢層の読者にも、「ちょっと変わった頭脳バトル漫画」というふうに受け入れられたんでしょう。
――『富豪村』の打ち合わせ時の印象は? 編集者として絡むのはそれが初めてですよね?
★マナー対決というテーマが決まったあとも先生から展開のアイデアがたくさん出て、こちらからも様々な意見を投げて、という形で進めました。他の作家さんと比べても頭からラストまでかなりしっかりと組み立てるやり方で少し意外でした。
――WJの現役編集者という立場で漫画家の卵や若い作家との付き合いもあるかと思いますが、『ジョジョ』リスペクトの人は多い?
★多いですね。クリエイターに与えている影響は尋常ではないと思います。若い作家が魅力を感じているのは、誰が見ても『ジョジョ』だとすぐに分かるところ。内容面でも圧倒的に尖っていて荒木先生しか描けないという唯一無二感です。実は先日、第2部をあらためて読み直して感じたんですが、バトルのアイデアの量が他の作品と比べて桁違いに、異常なほど多い。しかもこれを週刊連載でやっていたのか、という点に驚愕します。それとビジュアルの面白さですね。漫画の編集者になって分かったことですが、漫画の中でデザインやビジュアルの面白さというのはかなり大きいんです。特にスタンドは130体以上もデザインされていますが日本の妖怪や世界中の民芸品などを下敷きにしつつ、それらが先生の中で昇華されていて、シルエットが重ならない。
――人間キャラクターでも同じことが言えますね。
★それと、やりたいことを心おきなくやっているように見える点でもクリエイターは憧れると思います。ただ、先生自身は自分が描きたいものを描けばいい、というのではなく、例えば出てくるアイデアにしても、『富豪村』という読切1本の打ち合わせですら先生自身から「このアイデアじゃ読者は納得してくれないな」という言葉が5回くらい出たりする。「ここまでやらないと読者は喜んでくれないだろうな」というラインを、理屈ではなく感覚として持っている。決して好き勝手に描いているわけではないんですね。クリエイターに関して言うと、この数年の『ジョジョ』の再評価の動きはリアルタイムで読者だった人たちがクリエイターになって「『ジョジョ』が好き」と語っていて、そのクリエイターのファンも「じゃあ読んでみようかな」「『ジョジョ』ってオシャレかも」と手を伸ばした。物理的な理由としては、それがいちばん大きいと思います。あとはクリエーターたちが『ジョジョ』を語ることで昔からのファンの中にも「『ジョジョ』を好きと言っていいんだ」という安心感が生まれたんじゃないでしょうか。以前は『ジョジョ』好きというとマニアックとか思われがちでしたから。そういった古くからのファンの飢餓感も大きかったかもしれないですね、数年前までは『ジョジョ』はコミックスと画集以外のアイテムがほとんどなくて、僕らの『ジョジョ』への飢餓感はそりゃもうすごかった。そしてそのまま大人になった今はお金を使える世代になったから、今までの分を埋めるように沢山のアイテムに手を伸ばす、そういう構図もあると思います。
――荒木先生とのお付き合いで、印象に残っていることは?
★荒木先生との会食の時、道に迷って遅刻しそうになってレストランに駆け込んだら「レストランで走っちゃダメだよ」と注意されまして (笑)。それくらい公序良俗という部分をすごく意識されている方です。あとは『富豪村』でエピソードナンバーを入れてもらったことですね。先生は『岸辺露伴は動かない』の1作目『エピソード16:懺悔室』を描いた当時、「いくつか外伝がある中の1本というニュアンスが出せれば」ということで「エピソード16」としたらしいんです。ただ、先生の中でそこは比重の低いポイントだったらしくて2作目の『六壁坂』では実はエピソードナンバーが入っていない。僕は1作目を読んだ時に「残りの15本も読みたい!」とファンレターを書いたくらいの荒木ファンだったので、3作目の『富豪村』の打ち合わせの時に、先生はナンバーの件を完全に忘れていましたが (笑)、先生に「エピソード5」というナンバーを入れてもらいました。
――荒木先生と人柄や性格が似ている『ジョジョ』キャラクターは誰だと感じますか?
★よく岸辺露伴という話が出るんですが、僕の中ではまったく重ならないですね。似ていると思ったのは…、吉良吉影かな。規則正しい生活を送る部分や信念を曲げなかったり、という哲学が荒木先生に似ている感じがします。仗助と戦うことになった理由も自分の信念を貫いた結果なわけで、そこが先生の印象とだぶります。吉良の台詞は僕の脳内では完全に荒木先生の声で再生されるんですよね (笑)。
――荒木ファンの編集者という立場から見た荒木先生や作品の魅力は?
★個人的なことで恐縮ですが、高校時代は常に『ジョジョ』の第46巻と第53巻がカバンの中に入っていて (笑)。第46巻は仗助と吉良がにらみ合っているカバーイラストが大好きで絵の構図といいサブタイトルの「クレイジー・D (ダイヤモンド) は砕けない」といい、たまらない。第53巻は「ザ・グレイトフル・デッドの巻」ですが、フィレンツェ行き超特急の中という密室劇でありながらアクションも両立している点が素晴らしいエピソード。高校の帰り道はどちらかのコミックスを読んでいたので、それぞれ100回くらい読み込んだほどでした。中学2年生の時、たまたま読んだWJで『ジョジョ』と出会わなければ僕はまったく違う人生になっていたはずで、そんな感じで荒木先生は個人的には神様のような存在ですね。あ、でも実際に打ち合わせをした時は、ちょっと変わったところもあるけど普通の人という印象ではありました。ただ、ちょっと変わったところというのがポイントで、例えば映画で面白いと思うところが普通の人と違う。先生はジョージ・A・ロメロが監督した『ドーン・オブ・ザ・デッド (邦題『ゾンビ』)』という映画が大好きなんですが、どこが好きなのかと聞くと「ショッピングモールに生き残った人間が立て籠もって、好き勝手にしているところが好きなんだよねー」って。「そこですか⁉」みたいな感じのシーンですが、他の人が拾わないところを拾っていくのはセンスというか才能だと感じます。どんな映画に関しても、なぜ自分が感動しているのか、なぜ面白いと感じたのかが分析できていて、ものすごく頭のいい人という印象です。
――荒木先生が「ウルトラジャンプ」(以下、UJ) に移籍してからの担当ですが、そもそもの先生とのお付き合いはいつから?
★最初に担当したのは1999年の『デッドマンズQ』ですね。僕はその当時、「MANGAオールマン」という雑誌にいまして、そこに3号連続掲載というスタイルでした。「MANGAオールマン」の編集長が初代担当の椛島で、僕は荒木ファンだったので「担当したいんです!」と頼み込んで (笑)。
――『スティール・ボール・ラン』はUJ移籍当初、先生の中ではどういった構想だったんでしょうか。
★最初は「冒険レースもの。スタンドも出てこないかもしれない」というようなことを言っていました。ただ、途中から「謎を追いかける展開がほしい」という話も出て。たしかにそうなんですよね、第4巻の「週刊少年ジャンプ」(以下、WJ) 連載分までの流れで言えばゴールはあるけど、今ひとつ主人公の目的が見えない部分があった。レースに勝った負けたというだけの流れを繰り返していくと緊張感が保てないかもしれないし、プラスアルファの軸が必要だというのが荒木先生の中に出てきたんでしょうね。
――UJ編集部から先生へのオーダーは?
★少年誌ではないので、WJでは描けない残酷描写やセクシャルな表現もOKですという話はしました。先生の返事は「マニアックなものを描きたいわけではなく、王道を描いていきたい。ただ、少年誌ということで遠慮していた部分は挑戦として描くかもしれない」ということでした。WJは基本的に子供が読むものなので、いろいろ配慮しなければいけない部分もあるわけで。なのでオーダーは「描きたいことを思い切り描いてください!」ぐらいで、むしろ荒木先生に教えられることのほうが多いですね。
――具体的には?
★遺体争奪戦について打ち合わせをしていて「じゃあ敵に奪われた遺体を取り返す流れですね?」と聞くと、「いや、それだとプラマイゼロでしょう。何か得るものがないと。プラスがないバトルは意味ないから」と言われて、なるほどと思いました。荒木先生はよく「なんかグッとくるんだよね」という言い方をされるんですが、その具体例のひとつですね。プラスの爽快感があるということです。そういった荒木先生の理論とか方法論も勉強させてもらえたので、打ち合わせは楽しかったですね。荒木先生の言葉って最初に聞いた時は「え?」って思うことが多くて、例えば「次の敵はね、男尊女卑みたいな奴なんだよね」と言ったりする。第7部に出てくるリンゴォって敵キャラなんですけど。最初はイメージがつかめないんですが、よくよく話を聞いていくと、先生の「現代の男が弱っている感じがする」「だから強い男を敵で描いてみたい」という感覚が分かって、こちらも「ああ、なるほど」となるわけです。そういった時代の空気感も敏感に感じ取って作品に反映させていくタイプなんですね。
――絵柄に関しても空気感を取り入れるところはあるように感じます。承太郎の眉毛はしっかりしていますが周囲の漫画を見渡すと眉毛の細いキャラクターが主流になっていた。それで第4部の仗助の眉毛は細めに描いたとおっしゃっていました。
★そうですね。例えばフィギュアに関しても原型を先生に監修していただくんですが、第3部の承太郎の原型監修の時、先生から「承太郎の服装がさ、時代に合ってないんだよね」という意見が出た。そりゃそうですよ、20年前に描かれたわけですから。先生曰く「ウエストの位置が高すぎる。今は腰ばきだから、そうできないか」と。つまり先生の中でキャラクターデザインはアップデートされているんですよね。まぁ、でもファンが欲しいのは当時のキャラクターの立体物なわけで、その辺はお話ししたら「ああ、そうか」と納得はしていただけたんですけども。荒木先生の中では、過去の部のキャラクターやストーリーを新しくして今の感性に近づけることには躊躇がないんだろうと思います。
――フィギュアもそうですが、アニメーションやゲームなど、2010年頃から『ジョジョ』ムーブメントともいえるような大きな波が来ましたね。
★リアルタイムで『ジョジョ』の各部を好きだった人が、現場で決定権を持つ世代になってきたというのは大きいんじゃないかと思います。10年ほど前は現場の若い人が「『ジョジョ』をやりたい」といっても会社のOKが出なかったらしいです。ところがこの数年で、そういった『ジョジョ』好きな世代が決定権を持つ立場になってきて、合わせてお客さんも自由になるお金を持てる年代になった。需要と供給がはまったという感じでしょうか。そこに、今の若い世代も「『ジョジョ』っていう面白いタイトルがあるらしい」と気づいてくれて、裾野が一気に広がった感じがしています。これだけの会社や人間が「『ジョジョ』で仕事をやりたい!!」と手を挙げてくれるようになったのは、荒木先生がそういう作品を描き続けてくれていたからで、ひとえに作品の力だと思います。そして描き続けていたから歴代担当が社内のあちこちにいた、というのも大きいですね。例えば「ジョジョ展をやりたい」といえば宣伝部には東がいて『ジョジョ』のテイストに合う会場を探してくれたし、WJには瓶子がいて、上のほうには椛島や佐々木がいて…、という具合に荒木先生と『ジョジョ』を直接知っている人が要所要所にいるからとにかく話が早かった。そういう良い状況がいろいろと重なったんですね。
――裾野が広がって、従来のファン層とは違う若い世代や女性が増えているのも驚きです。
★ただ、気配はあったんですよ。UJに届くファンレターを見ていると「親子2世代で『ジョジョ』ファンです」という声がチラホラあった。中学生くらいの女の子からのハガキで「お母さんが読んでいたから、私も好きになりました。お母さんは第4部が好きで、私は第5部が好きです」みたいなことがあって、僕らも「えっ⁉」と驚くとともに、ムーブメントを作るのは女性で維持するのが男性という傾向がありますから「若い女子がいけるなら若い男子だっていけるかも?」という商売魂も出た (笑)。アパレルにしてもそうですね。2006年にユニクロとのコラボで荒木先生のイラストTシャツを出したんですが、僕らは「きっと年季の入った『ジョジョ』ファンが買うんだろう」と思っていた。ところが実は若い人が買っているというのが分かって、しかも、ものすごい売れ行きだという。その売れ方から、若い人たちは「読んだことはなくても、記号としては『ジョジョ』を知っているんじゃあないのか」「荒木イラストやスタンドを独特でカッコイイと感じてくれているのかな?」と気づかされた。例えば、スパイダーマンやバットマンというキャラクターはみんな知っているし、映画にも行くしフィギュアも買う。でも原作コミックは読んだことがないという人も多い。それと同じで『ジョジョ』という漫画は読んだことがなくてもスタンドやキャラクターは「なんかいいよね」って感じで受け止めてくれてるのかもしれなくて、そういう若い層がグッズを買ってくれるんじゃないか、もっとうまくいけば『ジョジョ』本編も読んでくれるんじゃないか、はまってくれるんじゃないか、というのはありました。もちろん当時は確証はなかったですけどね。
――結果的には、編集者としての読みが当たりました。
★でも、それは荒木先生の力ですよね。『ジョジョ』という長く続く作品にリアルタイムで食いついてくれた層がいて、若い人も絵柄も含めて独特でカッコイイと感じてくれたんでしょう。それに加えてフィギュアやアニメ、ゲームといった各ジャンルで『ジョジョ』好きが決定権を持つ年代になり、同時に集英社内のあちこちに歴代担当が何人もいてくれた。環境がすべて整っていたんでしょうね。もちろん荒木先生はそれを狙っていたわけじゃなくて、結果的にこうなったんですが。とても不思議なんですけど荒木先生ってそんなふうに、色々なものを呼び込む才能を持っているとしか思えないんですよね。大きなことも小さなことも含めて偶然という感じでもなく、先生自身が「自分はこうしたいんだ」という方向に本能的に向かって行くと、常に周囲が呼応していくような。途中で描くのをやめたりサボったりせずに、先生が「こうだ!」と思った作品を描き続けた結果が今という状況なんだろうなと。ひとえに「荒木飛呂彦だからこそ」というのがあると思います。褒め過ぎかもしれないけど (笑)。
――話は前後しますが、先生の第一印象はどうでしたか。
★意外にすごく気さくな人だな、と (笑)。最初にお会いした時、僕も御多分に漏れず「先生は岸辺露伴みたいに怖い人なんじゃないか」「馬鹿だと思われて一言も口きいてくれなかったどーしよー」と緊張していて、まともにしゃべれず背中に汗ビッショリでしたけど (笑)。そのあと、僕がいた「MANGAオールマン」という雑誌が2002年に休刊になって、UJに異動したんですが、先生がちょうど第6部を終えて少し時間ができた時に『変人偏屈列伝』シリーズの「ウィンチェスター・ミステリー・ハウス」「腸チフスのメアリー」の2本を描いていただきました。それが2003年頃ですね。「先生の体があいた時に、『デッドマンズQ』の新作も短期集中とかでやりましょう」という話もしていて、先生も「アイデアもいろいろあるし、吉良を描きたいんだよね」ということでした。そういえば当時、忘れられないことがありました。「MANGAオールマン」が休刊になって、僕の異動先もまだ決まってない時のことです。当時の部長が先生に「MANGAオールマンはなくなるけど、他にも読切を描く場所はたくさんあるからお願いします」という話をしたら、先生が「僕は井藤君が行く編集部で描きますよ」と言ってくれて。僕は感動して、「この人のことは絶対に裏切っちゃだめだ」と思ったんですね。社交辞令で言ってくれただけかもしれないけど、僕は救われました。本当に有り難いと思っています。
――先生がWJに第6部や第7部を連載されていた頃も『ジョジョ』の話は聞いたりしていましたか?
★第7部の『スティール・ボール・ラン』の連載直前の頃に先生から話を聞いたりはしていました。あの時期は荒木先生的にも悩んでいたんだろうなぁというのが僕の正直な印象ですね。ちょうどWJ編集部から「『ジョジョ』というタイトルを外して新作で」と頼まれていた頃だと思います。『スティール・ボール・ラン』が始まってからは、原稿を描きためるという変則的な仕事の仕方だったので「ペースが崩れた」ということも言っていました。週刊連載のような明確な締切がない中での仕事でしたから。自分が描きたい絵や構成に対して、ページ数が足りないという思いもあったんじゃないかな…。そんな時期に僕とふたりで食事をしている時に「ちょっと疲れたから、週刊で描くのはもういいかな」とポロッと言ったことがありました。「UJで描けないかな。月刊誌ならひとかたまりで描けるし。大自然とか馬も見開きの広い空間で表現できるしさ、WJの31ページだと窮屈なんだよね」という話も出ましたね。もちろん、僕としてはUJで描いていただけるなら大歓迎なんですが、まずはWJ編集部の意見を聞くのが筋なので、相談しに行きました。それと当時は「月刊少年ジャンプ」もあったんですが、先生にそこを聞いたら「知ってる人いないしさあ」と。
――人間関係を重視される?
★でしょうね。それで、いろいろとWJ編集部と調整して、話がまとまってUJで描くことになったわけですが、その時に先生が「で、UJでは何を描こうか。『デッドマンズQ』を描けばいいの?」と (笑)。
――そこは『スティール・ボール・ラン』の続きですよね (笑)。
★『スティール・ボール・ラン』はWJの連載分をまとめた第4巻のラストが「俺たちの戦いはこれからだ!」みたいな感じで終わっているでしょ? あれは先生的には、読者に一応の完結として見てもらってもいいように描いていたようですね。僕としてはもちろん『スティール・ボール・ラン』を読みたかったので、UJでも『スティール・ボール・ラン』をやりましょう、と。その時に荒木先生から言われたのが、「やっぱり『ジョジョ』というタイトルをつけたい」と。それでUJ掲載時から第7部と謳ったわけです。荒木先生の中では「やっぱり『ジョジョ』なんだよね」「『ジョジョ』って部が代わるごとに新連載みたいなものなんだよね」と言っていました。シリーズタイトルのようなイメージなんでしょうね。
――映画の『007』シリーズのようなイメージでしょうか。役者や舞台や年代が変わっても、やはりひとつのシリーズ。それと同じですね。
――第8部『ジョジョリオン』は立ち上げから関わっていますね。
★『スティール・ボール・ラン』の連載中から、「次は杜王町にしたい」とずっと言ってました。実は当初は第4部の杜王町を想定していて、途中で「1970年代が舞台なのもいいね」みたいな話も出ていました。荒木先生の少年時代ですね。ただ、それだと携帯電話やメールが使えないとか、物語上の制約も増えるので、逆に近未来を舞台にしようかというアイデアもありました。
――『ジョジョリオン』は主人公像が異色ですね。記憶喪失で睾丸を4つ持っている。
★僕個人の印象なんですが、2011年の東日本大震災のあと、日本中の人々がある種の喪失感を抱いていたと思うんです。僕たちはこれからどうしていけばいいのか? そもそも日本人って何だろう? そういったことも含めて単純に「敵がいて戦って」というだけでなく、「自分とは何者なのか?」を探しにいくのがテーマなのかな、だから記憶喪失なのかなとは思いました。荒木先生自身はそういうテーマを表に出すのが嫌いな人なので、ハッキリ語らないでしょうけど。荒木先生は直感的に、物事の本質をとらえる力がすごく鋭い漫画家さんだと感じています。以前、雑談の中でいじめ問題について話したことがあったんですが、先生は「いじめは良くないとか、やめましょうとだけ言うのは良くないと思うんだよね」と。「戦争にしても、世界平和は理想だけど、現実には戦争は起きてしまう。いじめも現実にはあるんだから、大事なのはいじめにあった時にどう向き合うかを教えてあげることじゃあないか」「きれい事だけ言われたら、子供はキツイと思う」と。その通りだと思います。先生も子供の頃にきれい事を色々と言われた時、「映画館でホラー映画とかを見ると安心した」って言うんです。何故かというと、そこでは当たり前ですが残虐なことが起きるわけで、でも主人公たちがどう向き合うかを見せてくれる。「嘘がない空間だったんだよね」ということを言っていて、この人はすごいと思いました。「ホラー映画を見ると安心する」っていう部分だけを切り取ると単なる危ない人になるんですけど (笑)、真意を紐解いていくと実は本質を突いているんです。これも以前の話ですが、大学生のフリーペーパーの取材で「就職とか色々と決断しなくちゃいけない学生に大事なことは?」という質問を受けたときの答えが「美しさっていうのかな。そういうのが大事なんですよ」って。聞いたほうは「え?」ってなったと思いますよ (笑)。で、どういう意図なのかを聞いていくと、「自分にとって、美しいとか良いと思えることを判断できる審美眼を学生時代に磨いてほしい。その判断ができれば、決断もできるんですよ」っていうことなんだと。そういった荒木理論に『ジョジョ』は裏打ちされて描かれているんですよね。
Q: The Morioh in Part 4 and the Morioh in Part 8 have the same name but are different places. They exist in parallel worlds. But was there any consideration to have Part 8's Morioh be the same as Part 4's?
Yamauchi: As far as I know, there was no such discussion. I remember we talked about having the setting be similar to Part 4's to make readers smile. But I don't think we ever talked about setting the story in the same town. Oh, but we jokingly remarked, "Rohan being there might be fine." After all, he managed to complete his manuscripts on time even during the climax of Part 6, where time was accelerating, so there's a possibility that he exists beyond time and space (laughs).
――担当になったタイミングは、『スティール・ボール・ラン』のどの辺りからでしょうか。
★2011年2月に新担当として先生に紹介されました。『スティール・ボール・ラン』のラストも見えていた時期ですね、前任の井藤からの引き継ぎも兼ねて『スティール・ボール・ラン』の打ち合わせには2回ほど同席しましたが、もうラストまでの流れは決まっていたので特に口出しすることもなく、「先生はこういうふうに打ち合わせをしているのか」という確認をしていました。
――その後、第8部である『ジョジョリオン』に突入するわけですね。
★『ジョジョリオン』第2話くらいまでは井藤と一緒に打ち合わせに行ってたかな。話題を呼んだ『ジョジョリオン』というタイトルはその頃に荒木先生から出たものです。ちょうど作家デビュー30周年と『ジョジョ』25周年の期間が始まった頃ですから、『ジョジョリオン』第2巻の先生のコメントにもあるように「記念碑的な意味も込めて」のようです。覚えやすくてキャッチーで、意味は分からなくても一言で言えて、『ジョジョ』性が高い感じもある、良いタイトルだと思います。杜王町が舞台となることは僕が担当する前から決まっていたんですが、担当になってから変わった部分もあります。ひとつはやはり東日本大震災ですね。「杜王町を舞台に描く以上、震災に触れないわけにはいかない」とおっしゃっていました。また、時代設定までは決まっていなかったのですが、必然的に震災後、つまり現代が舞台となりました。
――杜王町に関しては、数年前のインタビューでも「あらためて描きたい」といったお話が出ていました。
★『ジョジョリオン』の舞台が杜王町になったのは、ある種の必然かなという感じはしています。第3部でエジプトまで旅した後に、第4部は先生の故郷である仙台をモデルとした杜王町を描きましたよね。今回も第7部がアメリカを旅する物語でしたから、それに続く第8部で杜王町というのは、故郷に帰る安心感みたいなものがあったんじゃないかと思うんです。作業の面でも、地理的にも時代的にも異国のアメリカと違い、ご自分の中の原風景を現代的に組み立てていけばよい杜王町は、サスペンスやバトルの描写により集中できる舞台なのではないでしょうか。
――第4部の杜王町と第8部の杜王町は、名前は同じですが違う場所でもありますね。並行世界的なものですが、第4部の杜王町にしようという案は無かったのでしょうか。
★僕が知る限り、そういう話はありませんでした。第4部を読んでいる読者がニヤッとできるような設定があったりしたらいいよね、という話はした記憶がありますが、そのまま同じ街を舞台にするという話をしたことはないと思います。あ、でも「露伴はいてもいいかも」という話は、冗談交じりで話しましたよ。なにしろ時間が加速した第6部のクライマックスでも原稿を間に合わせた人ですから、時空を超えて存在する可能性がある (笑)。
――歴代の担当編集によると、荒木先生は連載をしながら先の展開を考えるタイプとのことですが、『ジョジョリオン』も同じでしょうか。
★同じですね。先々をガッチリ決めて描かれてはいません。だから予定調和にならず、続きが気になって仕方がない作品が描けるんだと思う。漫画はクライマックスに向かって螺旋を描いて展開するのが良い、という話を先輩から聞いたことがあるんですが、それで言うと『ジョジョリオン』は、まだ螺旋の大きさもスピードもはっきりとは分からない状態です。だからこれまでに登場したお話のパーツがフッと繋がると、ものすごい勢いでストーリーが展開していく可能性があります。逆にまだこれから新たな謎が現れ、螺旋の直径が大きくなる可能性もあると思いますよ。荒木先生の場合、どこかに行ったと思っていた設定や展開が、ある日の打ち合わせで突然復活してくることも多いので (笑)。『ジョジョリオン』のラストがどうなるのかという話も、先生からまったく出ていません。定助が何者なのかという、彼の謎を解き明かす物語にはなっていきますが…。
――2010年頃から『ジョジョ』の一大ムーブメントが発生しています。ここまで広がったきっかけは担当から見て何でしょうか。
★潜在的な人気はもともとあった作品だと思うんです。きっかけのひとつは、時を経て『ジョジョ』を好きな世代が様々なメディアで決定権のある立場になり、作品や商品、さらには先生ご本人のメディア露出が増えたから、というのがあると思います。もうひとつは、これも世代的なものがあるかもしれませんが、クリエイターをはじめとした、別ジャンルで活躍する発信力のある方々がその分野でトップに立ち、『ジョジョ』ファンを公言するようになったことです。彼らの作品のファンが「原点」を探った結果『ジョジョ』に辿り着き、新たなファンになるという、ジャンルや世代を超えた拡散があったのではないでしょうか。面白いのは、そういった『ジョジョ』好きの方々は、ただ「好きだからコラボしたい」というタイプではないんですね。皆さんご自分なりに、『ジョジョ』を咀嚼して消化し血肉とした上で、ご自分のアウトプットをされているんです。それができるからトップに立っている、ということもあるんでしょうけど、『ジョジョ』ならではの特徴だと思います。それは漫画でも同じで、『ジョジョ』に影響を受けた作家はすごく多いのですが、そのままストレートに出す作家はいないし、実際に亜流の作品はまったく見当たらない。荒木先生ご自身が、他のカルチャーを創作のヒントに取り入れているのと相似形で、興味深いですね。
――ムーブメントに火が付いたとリアルに感じたのはどのタイミングですか?
★前任の井藤が担当した『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』が出版された2011年あたりですね。オールカラーの大判コミックスとはいえ、定価2800円の本が発売されて即日重版がかかったんです。想定を大幅に上回る売れ行きでした。ネットの掲示板で『ジョジョ』のセリフが扱われたりメディア露出が増えていたりと、漠然とした雰囲気を感じてはいましたが、具体的に意識したのはこの出来事です。『ジョジョ』がスタートしてから、20数年間かけて熟成されていたものが、一気に跳ねた、ということなんでしょうね。
――このムーブメントの大きな背骨となったのが、2012年に開かれた「荒木飛呂彦原画展 ジョジョ展」ですね。先生の故郷である宮城県仙台市、そして東京の2ゕ所で開かれました。
★両会場とも、予想を大幅に上回るお客さんに来ていただけました。東京会場は約1ゕ月という長期の展示でしたが、実は企画立ち上げ当初は2週間くらいの予定だったんです。それでも、今だから言えますが個人的には一抹の不安を持っていました。すでに『ジョジョ』がいわゆる「ブーム」な状況で話題になっていたし、コミックスもすごい勢いで重版がかかっていましたが、開催する10月は休日の少ない時期です。原画展に来るほどのファンはやはり男性サラリーマンが中心だろうと読んでいましたから、例えば「平日の昼間に来てくれる人なんかいるんだろうか?」と。ところが蓋を開けてみたら平日の昼間でもチケットは全て前売りで、しかもかなり早い段階で完売。お客さんも若い女性からお子さんまで非常に幅広く、本当に驚きました。ご覧いただけない方もたくさん出てしまい、それは本当に申し訳なかったのですが…。
――2011年には雑誌「SPUR」10月号の別冊付録でGUCCIとのコラボレーションが実現し、それが縁で2013年には荒木先生のイラストがGUCCIの全世界直営ショップのウインドウデザインにも選ばれました。
★GUCCIに関しては90年を超える歴史と伝統があり、ハイクラスの方に愛されている超一流のブランドです。荒木先生のイラストがショップのウインドウビジュアルとして使われたのは、先生の絵がハイクラスのお客さんに価値が理解されるものだと認められたからでしょうね。あれだけのハイブランドが全世界で展開するウインドウビジュアルを、『ジョジョ』というひとつのキャラクターに賭けるというのは大変な決断だと思います。これは荒木先生の絵が持っている力なんでしょうね。そして2013年6月にはGUCCIの協力で、イタリアのフィレンツェで原画展が開かれました。
――2012年には雑誌「SPUR」の増刊ムック「ジョジョメノン」も発売されています。この本で荒木先生は、承太郎のイメージの源流でもある俳優のクリント・イーストウッド氏とも会いましたね。
★あんなに舞い上がる先生を見たのは初めてです (笑)。例えば写真撮影の時は、カメラマンからお互いに見つめ合うポーズをオーダーされて「いやー! 眩しくて見られないですよー!」という感じ。本当に子供のように喜んでいらっしゃいました。日頃の打ち合わせでも、イーストウッド氏への敬意を聞いてはいたんですけれど、「本当に憧れの存在なんだな、喜んでもらえてよかった!」と、僕まで嬉しくなりました。もちろんイーストウッド氏は簡単に会えるような方ではないんですが、いくつかの幸運がタイミング良く重なって実現しました。歴代担当や関係者ともよく話すんですが、荒木先生は本当に「運を持っている」としか思えないんですね。「幸運が重なって」と言いましたがイーストウッド氏が興味を持ってくれたのもルーヴル美術館やGUCCIとのコラボレーションという実績があったからだと思うし、それらも先生がずっと『ジョジョ』を描いてきたことの結果であって、単なる幸運ではないと思っています。
――少々ベタな質問ですが、荒木先生が似ている『ジョジョ』キャラクターは誰だと感じますか。やはり岸辺露伴?
★キャラクターそれぞれの、いろんな面をお持ちだと思うんですよね。意外なところでは、確信を持って行動し、進んでいくという点で第7部のヴァレンタイン大統領みたいな面もあるし。先生の人柄についてだと「公序良俗に反することはやらない」という部分は僕も印象が強いですね。例えば荒木先生は絶対に信号を守るんですよ。幅の狭い道で、深夜の車がまったく走っていないような時間帯でも、先生は赤信号であれば渡らない。人が見ている見ていないは関係なく、自分の中で後ろめたいと思うことはしたくないんじゃないかな。
――漫画の執筆に加え、原画展、様々な取材や関連本の発売など、2011~2013年の荒木先生は相当な忙しさではなかったでしょうか。
★色々な場所に行ったり、イーストウッド氏をはじめ様々な人と会えたりと、「普段ではできない経験を楽しんでいる」とおっしゃってはくださいましたが、ものすごくお忙しかったと思いますよ。あれほどお好きな映画を観られない時期があったくらいですから…。担当してまだ2年と少しですが、僕ほど荒木先生にお願いごとをした担当っていないんじゃないですか (苦笑)。でもそんな無茶振りにいつも応えてくださって、頭が下がるばかりです。先生は人一倍漫画を描くことに労力を投入する方ですが、それは必ずしも原稿用紙と向き合うことだけではないんですね。映画を観たり美術品を見たり、人と会って話したことなどを作品に投影させていくことを含めての「人一倍の労力」。すごい才能だと感じます。作家さんに限らず、たいていの場合は「仕事をしなきゃ」という決意の中で色々なことを進めると思うのですが、先生の中にはおそらくそういう意識があまりない。漫画を描くためのあらゆる才能を持っている人で、これはもう荒木飛呂彦というひとつのジャンルだと僕は思っています。
Commentary
編集者インタビューを読んだ荒木先生から一言!
「僕、行きますよ」って言ったら「いや、来ないでくれ」と。 (佐々木)
★ああ、これは多分リズムが狂っちゃうからじゃないかなあ。ストーリーを考えたり原稿を描いている時に突然、打ち合わせってなると作業を止めなきゃなんない。特に週刊連載の頃は作画時間が週3日しかなくて、単純計算で1日6ページくらい描くっていう結構タイトな進行なんです。そこで1時間でもロスすると睡眠時間を削ることになるから、それで多分「来ないで」と言っちゃったんだと思います。
吉良を出すのが決まったタイミングはそこですね。 (垣内)
★日常のバトルをもっと描きたかったから「今は吉良を出すタイミングではないかもしれない」「出したら第4部は完結へ向かうかもしれない」っていう気持ちもありましたね。吉良は承太郎と康一に一度敗北して顔を変えて逃げるんだけど、敵って敗北のあとに復活してからが強いと思うんですよ。「負けを知っている人間がいちばん恐ろしい」ってことですね。
先生からは「主人公を女性にしたい」という話がありました。 (関谷)
★憶えてないなぁ…。ただ外国映画でも主人公が女性弁護士だったりする「強い女性」を描いた作品が出ていた頃なので、新鮮な感じがしてたと思います。第1部から第3部までは神話的世界というか「強くて逞しい男」がテーマのひとつだったので、そこからの脱却というのも第5部の頃にはあったと思いますよ。
スケッチブックの他にノートが (東)
★1999年から使っている、スタンドのアイデアをメモしたノートですね。ちょっと中は見せられないんだけど…。他にもアイデアノートは昔から作っていて、そっちはもう何冊もありますね。中身はキャラクターの背景をメモしたキャラ身上書とか話の展開のメモとか。それと「銀杏の葉はなぜ滑るのか」みたいなメモもいっぱい書いてある。くだらないネタに思えるかもしれないけど、これが何年かして熟成されると活きてくるんですよ。あと、「この映画、つまんねーっ。カネかえせー!」みたいな感情もちょっと書いてある (笑)。
(順位は)まったく気にされませんでした。 (嶋)
★読者の人気を取るためにストーリーを作ると流れに違和感が生じるんですよ。例えば読者の要望があるからといって、第2部のカーズが地球に戻ってきても、必然性がなければ自然な感じじゃなくなると思うんですよね。でも、そこは本当に難しいですね。観光地は宣伝してお客さんに来てもらいたい反面、人が入らないようにして自然や伝統を守らなくちゃいけない。同じようなせめぎ合いがあるんですよ、漫画にも。
段階を踏んでWJではない何処かに移籍する (瓶子)
★読者にたっぷり読んでもらいたいっていう気持ちは大きくなっていましたね。毎週19ページのWJだと、もうページが足りないんですよ、19ページの呪いっていうか (笑)。WJでの『スティール・ボール・ラン』は特殊な連載形式を試させてもらったけど、逆に仕事のリズムが崩れてしまって自分には全然合わなかった。だけど月刊誌なら1話が45ページくらいなので山場を2回、自由な場所に作れるからサスペンスもタップリと分かりやすく描ける。それで「これだったら月刊誌に行ったほうがいいな」と思ったんです。
デザインやビジュアルの面白さ (齊藤)
★シルエットは大事ですね。以前、電車の中でWJを読んでいる人がいて、遠くからそれを見てたのにキャラクターのシルエットだけで「あの人、超人気漫画の『○○○○』を読んでる!」って分かったんですよ。そこはスゴイと思ったし、「それに負けちゃだめだ!」って思ったからシルエットはかなり気を遣います。他の作品の良い部分は取り入れないといけないですね。
「(ウルトラジャンプでは)『デッドマンズQ』を描けばいいの?」 (井藤)
★え~、こんなこと考えてたかなあ (笑)。僕はUJでも『スティール・ボール・ラン』を描こうと思ってましたよ、だってゴールさせないと (笑)。ただ、実はWJの時もUJの時も、「本当にゴールできるのか⁉」と自分自身が不安な部分はありましたね。最初にハッキリとコースも最終地も見せちゃったので、破綻したら後戻りが出来ない物語でしたから。最初に全体を見せてあえて自分を追い込んだんだけど、ニューヨークにゴールできて本当に良かったぁ (笑)。
先生の絵がハイクラスのお客さんに価値が理解されるものだと認められた (山内)
★ファッションに行けたのは僕にとって大きいですね。ファッションはクールさが魅力なわけで、例えばモデルの写真もわざと目線を外したりしてる。でも少年漫画は正反対で、キャラの目線はビシッと読者に向けなきゃいけない。その正反対の水と油のところに僕を呼んでいただけたというのがびっくりだし、有り得ないことだと思っていたので、自分の中では画期的ですね。
Notes
- ↑ "ikemen" (イケメン) means "handsome/good-looking guy" in a trendy or cool way. Since this was before its trendy definition, the English loanword "handsome," spelled "hansamu" (ハンサム), was used instead.
- ↑ In Nostradamus's book Les Prophéties, he writes: "The year 1999, seventh month, will come from the sky a great King of Terror. Resurrect the great King of Angolmois, before after, Mars will reign by good luck." This prediction is typically interpreted as the beginning of the apocalypse. It should also be noted that, from the introduction of Mikitaka onward, the rest of Part 4 takes place in July, the seventh month of 1999.
