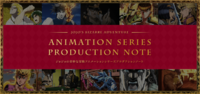Anime Production Notes (03/2021)
Vizmedia (October 2020)
In commemoration of "JOESTAR The Inherited Soul", the production notes of the successive "JoJo Anime" series have been released!
"How was" the Jojo Anime "made?" The answer will be delivered in a series of four times, with the testimony of the main staff, including Naokatsu Tsuda, who was the director in all seasons. The burning Jojo love of successive directors and producers explodes!
Interview
Vol. 1
荒木飛呂彦の才能にチーム戦で立ち向かう! 『ジョジョアニメ』を駆け抜けたクリエーターたち
アニメ化の幕開けは「これは難題だ」
ワーナー ブラザース ジャパンの大森啓幸プロデューサーは、とあるアニメ関連企業からTVアニメ化の話を持ちかけられた際、「これは難題だ」としばらく悩んだという。日本を代表するビッグコンテンツのひとつではあるが、なにしろ原作の発表は1987年である。とくに初期の荒木飛呂彦が描くキャラクターは劇画調でマッチョイズムに溢れており、少なくとも現代の流行の絵柄とはかけ離れていた。ジョジョを知らない層は、はたして受け入れられるのだろうかと。しかし大森は「絵柄をどうするかという問題はありましたが、作品そのものがもつパワーはけして色褪せてはいませんし、なにより僕自身が大のジョジョファンということもあって、困難を承知で挑戦させてもらうことにしました」と、アニメ化を決意。集英社からの快諾も得て、さっそくスタジオ選びに着手することになる。
ジョジョを描くことのできるスタジオとなると、当然「力強い筋肉の躍動が描けるスタジオ」ということになる。そこで大森は、かつて骨太な作品を数多く手がけていたGONZO(ゴンゾ)の流れを汲むdavid production(デイヴィッドプロダクション)に着目。当時のデイヴィッドはまだ設立したばかりの新興スタジオだったが、ジョジョと同じくジャンプ系列作品である『戦う司書』シリーズを力強い描線で丁寧にアニメ化していたことを受け、大森は「ここならば任せられるだろう」と確信し、打診に及んだという。
荒木飛呂彦の才能に、チーム戦で挑む
アニメ化の知らせを受けたデイヴィッドプロダクションの笠間寿高プロデューサーが考えた秘策は、複数監督体制だった。「たぐいまれなる荒木先生の才能を、ひとりの監督で引き受けるのは正直難しいと思ったんです。TVアニメの座組としては珍しいのですが、監督を複数体制にして、チーム戦で挑むことにしました」(笠間)。白羽の矢が立ったのは、津田尚克と鈴木健一のふたり。津田は「監督」、鈴木は「シリーズディレクター」とクレジットに多少の違いはあるものの、実質的にはすべての作業を協業する形で制作に取り掛かった。
笠間は津田と鈴木のふたりを起用した理由について「津田さんはコメディに強く、鈴木さんはアクションに強い演出家。このふたりが協力することで、原作の力強さと面白さのどちらの魅力もすくい取れるのではないかと思った」と話す。実際、津田も「僕自身もジョジョファンではありますが、僕ひとりで作れと言われていたら断っていたかもしれません。鈴木さんといっしょということで、それならできるかもと思ったんです。今思うと若気の至りというか、怖いもの知らずでしたね(笑)」と当時を振り返った。一方の鈴木は「プレッシャーはとくになくて、大好きなジョジョに携われるという喜びのほうが大きかったです。大きなタイトルですが、あまり周りの意見に惑わされることなく、僕と津田君のジョジョを作ろう」と意気込んだ。
こうしてプロデューサーの大森と笠間、ディレクターの津田と鈴木という中核メンバーが揃ったが、奇しくも4人全員が大のジョジョファン。フィルムの隅々から感じる原作へのリスペクトは、この布陣を考えればむしろ当然の結果なのかもしれない。また編集部の推薦により小林靖子がシリーズ構成として参加。さらにビジュアルディレクターとしてソエジマヤスフミが加わり、いよいよジョジョアニメは走り出す。
「ジョジョっぽいもの」ではなく「ジョジョを作る」
制作チームに対し、大森プロデューサーが最初に相談した方向性は「ジョジョを作る」ことだった。「ジョジョっぽいもの」や「ジョジョらしいもの」ではなく、ジョジョそのものを作るということ。それを受けた津田たちは、再度原作をボロボロになるまで読み込み、ホワイトボードに思いつく限りジョジョの要素や特徴を書き出していった。「擬音」や「独特なポージング」といった分かりやすいものから、「読後感スッキリ」、「バトルが難解」といった印象に至るまであらゆるものを出し尽くす。そして最後にそれらを整理していくのだが、「一般的なアニメーションの作法に則って作る限りは、どうも"ジョジョの平凡な冒険"になってしまう。ジョジョはあくまで"奇妙な冒険"でなくてはなりません。そう考えると答えは最初からタイトルにあったんですよね」(笠間)との結論に至る。
こうして「擬音」をはじめとしたすべての要素の完全再現を追い求めることで全員が一致。この会議を通じて設けられたルールはのちにジョジョアニメに関わるすべてのスタッフに配布され、以降のシリーズを通じて「バイブル」として機能することになった。
冒頭3話で視聴者を惹きつける!
ジョジョアニメは、最初から4thシーズンまでの制作が約束されていたわけではない。1stシーズンで一定の成果を得られなかった場合には2ndシーズンの制作は行われないという状況で、大森プロデューサーがとくに注力したのは冒頭3話だった。
そもそもジョジョと言えば「スタンドバトル」のイメージが強く、スタンドが登場した原作第3部「スターダストクルセイダース」で多くのファンを獲得した作品である。それだけに、ともすれば地味に思われがちな原作第1部「ファントムブラッド」をどう扱うかは大きな課題だった。そこで大森は、視聴者が冒頭3話でジョジョの世界観にどっぷりと浸かってくれるように心掛け、アニメスタッフは最初の山場となる原作17話までを冒頭3話で一気に描き切った。通常アニメの1話は漫画の3、4話分に相当するのが一般的だから、これがいかに思い切った構成かがよく分かるだろう。大森曰く「ジェットコースターのような展開にすることで、視聴者に夢中になってもらいたかったんです」とのこと。
この展開は功を奏し、多くのファンに好意的に受け止められた。リアルタイムでSNSの反応を追っていた大森は「これでひとまず大丈夫かもしれないと、心からホッとしました」と述懐する。
人気の「スターダストクルセイダース」は 最強布陣でクオリティアップ!
1stシーズンの好評を受け、放送終了後すぐに制作チームは2ndシーズン「スターダストクルセイダース」(原作第3部)の制作へ移行。2ndシーズンはスタンドによる激しいバトル描写が最大の魅力で、シリーズでも屈指の人気を誇る絶対に落とせない部。そのため1stシーズンと比べて作画枚数を増やし、新たにアクション監督を迎え入れるなど作画面での強化が図られた。また演出面でも、1stシーズンで中心的な役割を果たした加藤敏幸が新たにチーフ演出を務め、より安定した演出体制を確立。
こうして4シーズン中最長となった全48話を、終始安定したクオリティで駆け抜けることに成功した。1stシーズンから追い求めていた「筋肉の躍動美」は円熟味を増し、フィルムとしてひとつの完成形を迎えたと言える。
3rdシーズン「ダイヤモンドは砕けない」(原作第4部)は 異色作ゆえ、ガラリと方向転換
日本からはるばるエジプトを目指すロードムービーだった2ndシーズンから一転、3rdシーズンは杜王町という小さな街が舞台となる。別作品を監督するためジョジョを離れた鈴木に代わって監督に就任した加藤は、これまでとは毛色の違う作風を正確に把握するため、再びチームでブレストを開催。
「第3部までは物語の目的がはっきりしていたんですが、第4部はゴールがどこにあるのかわかりにくいんですよね。そういう意味ではかなり特殊なので、方向性については徹底的に議論しました」(加藤)。
その結果、ラスボスである吉良吉影の猟奇シーンを冒頭に挿入するといったさまざまな工夫を凝らし、ストーリーの魅力を損なうことなく原作を大胆に再構成してみせた。
新監督を迎え、さらに進化した 4thシーズン「黄金の風」(原作第5部)
3rdシーズンで監督を務めた加藤が別作品の監督を務めることとなり、ジョジョアニメから離脱。1stシーズンから作品の中核をになってきた鈴木・加藤という両翼を失ったことにより、津田は新戦力を求めて自らのツテを駆使し、木村泰大と髙橋秀弥を口説き落として新監督に就任させる。津田は「第5部における僕のいちばんの功績と言えば、木村さんと高橋さんを監督に、岸田隆宏さんをキャラクターデザインに引き入れたことです」と言い切るほど。
こうしてジョジョアニメ未経験ながら新監督となったふたりは「最初こそ僕にジョジョのコンテが描けるのか不安でしたが、思っていた以上に自由度が高いことがわかり、ノビノビとやれました」(木村)、「僕と木村さんは個性がまったく違っていて、結果的にお互いの個性がよく出たシリーズになったと思います」(高橋)と、それぞれの才能を存分に発揮する。津田が4thシーズンで掲げたテーマは、物語の舞台であるイタリアにちなんで「ルネッサンス(原点回帰)」。両監督がゼロからジョジョアニメの原点に立ち返ることで津田の狙いは見事に達成され、さらに綿密なイタリアロケハンの成果もあって、シリーズに新しい風を吹かせることとなった。津田が手がけてきたジョジョアニメの集大成であり、現時点での最高到達点である。
ジョジョアニメ、その「受け継がれる黄金の魂」とは?
単行本63巻に及ぶ壮大な大河ドラマを、約7年間をかけ計152話で描いたジョジョアニメ。監督の津田尚克やシリーズ構成の小林靖子、音響監督の岩浪美和をはじめ、全ての部に携わっているスタッフもいる一方で、途中退場したスタッフや新たに途中参加したスタッフも少なくない。「バイブル」をベースにしつつも、シーズンごとにビジュアルコンセプトが一新されていくジョジョアニメ。新陳代謝を繰り返しながらも前進し続ける制作チームは、まるで「受け継がれる黄金の魂」そのもの。これからもさらなる進化を遂げながら、新しい世代へと受け継がれていくことに期待したい。
取材・文/岡本大介
Vol. 2
「『ジョジョ』とは何か?」を徹底的に分析アニメでの完全再現に込められた想いとは?
「ジョジョを科学する」という発想で原作を再現
ジョジョアニメを制作するにあたり、ワーナー ブラザース ジャパンの大森啓幸プロデューサーからの要求は「ジョジョを作る」というごくシンプルなもの。それを受け、監督の津田尚克が掲げたスローガンは「ジョジョを科学する」だった。
原作の特徴であり、ジョジョをジョジョたらしめる要素を全て拾い上げ、アニメーションで再現する方法を模索。「メメタァ」や「ゴゴゴゴゴ」といった独特な擬音、個性的なポージング、「そこにシビれる! あこがれるゥ!」といった舞台的な台詞回しなど、誰もがイメージするものはもちろんのこと、集中線の使用や画面内のコマ割り演出などもアニメで徹底的に再現した。
1stシーズンから演出を務める加藤敏幸は「不気味さを演出するために、原作では霧や煙のような名状しがたい気体が渦を巻いている描写がけっこうあるんです。通常であればこれらはCGで処理してしまうんですが、そこは原作そっくりに手書きで再現しています。ほかにもキャラクターの不穏さを表現したい場合に、顔全体にトーンを貼って暗くして、目だけに光を当てるといったサスペンス的手法も原作通りに取り入れています」と語っており、スタッフ陣のこだわりが随所に見て取れる。
「シーン特色」はアニメならではの醍醐味
映像演出で特筆すべきは、「シーン特色」や「カット特色」と言われるカラー表現だ。ジョジョファンならご存知の通り、ジョジョのカラーリングには決まった色が存在しない。荒木飛呂彦が描くカラー原稿は、同じキャラクターでもそのときどきによって色がガラリと変化することはよくあることで、むしろ決まった色に捕らわれないことがひとつの個性となっている。
とは言え、基本的にモノクロで描かれる漫画原稿とは違い、アニメーションはつねにフルカラー。シーンごとに色がコロコロ変化するわけにはいかない。そこで津田たちは、全体のベースとなる基本色を決めたうえで、展開に応じて色を変化させる「シーン特色」や「カット特色」を採用。キャラクターの心情が大きく揺さぶられたり展開の山場などで使用され、アクセントとして効果的に機能している。アニメーションの特性を存分に生かした発想で、大きな強みとして4thシーズンまで踏襲された。
キャラデザはファンがイメージする中央値を模索
1stシーズンのビジュアル構築において、とりわけ試行錯誤したのがキャラクターデザインだ。というのも、初期の荒木飛呂彦が描くキャラクターはみな筋肉隆々で画風も劇画に近い。現代の流行とは言い難く、このギャップをどう埋めるかが課題となった。そこで制作チームは、多くのジョジョファンがイメージするキャラクター造形が原作第3部から第5部であることから、その中央値を1stシーズンに還元することで、よりファンの心象イメージに近いキャラクターデザインを作り上げていった。こうして出来上がったキャラクターたちは、初期の荒木キャラならではの濃い雰囲気も残しつつ、全体的にマイルドでカジュアルな造形に落ち着いている。
19世紀から現代まで! 美術の変遷
部ごとに時代や舞台がガラリと変化するのもジョジョシリーズの特徴だけに、美術や設定作業も大変な苦労を伴った。1stシーズン「ファントムブラッド」は19世紀末のイギリス、「戦闘潮流」は第二次世界大戦前のアメリカやヨーロッパが舞台となるが、これらは原作でも現実に即した形では描かれていないため、アニメにおいてもある意味ファンタジーとして描かれた。しかし続く2ndシーズン「スターダストクルセイダース」となると、時代は1980年代で、日本からエジプトに至るさまざまな国と地域が舞台となる。建築物だけでなく、行き交う人々の民族や服装も多岐にわたるため、美術班だけなくサブキャラクターデザインの負担は相当なものになったという。
またプロップ(小物設定)についてもこだわっており、例えば第37-38話の「地獄の門番ペット・ショップ」の脚本と絵コンテを担当した鈴木は、原作に登場するポルシェの車種について、通称・イエローバードと呼ばれる限定生産モデルなのではないかと推測し、設定に取り入れている。「この時の敵スタンドが鳥で、そこにポルシェが突っ込んでくるので、おそらく当時の荒木先生もイエローバードを想定していたんじゃないかと思ったんです。まあ完全に想像なんですが(笑)」(鈴木)。正直なところ、原作に数コマ登場しただけの車についてここまで考察を広げる必要はないのだが、それこそがジョジョ愛がなせるこだわりだろう。
3rdシーズン「ダイヤモンドは砕けない」はこれまでとは一変して、最初から最後まで架空の街・杜王町が舞台となる。監督を務めた加藤は原作をもとに精密な杜王町の地図を作り、各キャラクターの家や学校までの通学路、所要時間など、作中で行われる移動のルートを細かく計算。「杜王町は第4部のもうひとつの主役だと思っているので、できるだけ実在感を出したかったんです。誰もが馴染みのある日本の片田舎の風景と、その裏で起こっている凶悪な殺人事件という対比を強調するためにも、町の作り込みには時間をかけました」(加藤)。
4thシーズン「黄金の風」の舞台は2001年のイタリア。総監督の津田、監督の木村泰大、髙橋秀弥らは2017年7月にロケハンのためイタリアへ渡航。「聖地巡礼をしやすくしようというのは最初から目標にしていた」という木村の言葉とおり、作中に登場するほとんどの場所を突き止めた。この綿密なロケハン作業の成果はフィルムに空気感としてしっかりと閉じ込められており、視聴者はジョルノたちとともにイタリア全土を旅行したような気分になれる。
作画における「ジョジョイズム」の確立
デイヴィッドプロダクションの笠間寿高プロデューサーは、最初にジョジョのアニメ化を聞いた際、「この絵柄を動かせるアニメーターがどれだけいるだろうか?」と不安を覚えたという。たしかにデイヴィッドプロダクションは濃い絵柄を動かすことが得意なスタジオではあるが、それでもここまではっきりと筋肉や骨格が強調された作品はこれまでに経験がなく、スタジオとしても大きな挑戦だった。1stシーズンでシリーズディレクターを務めた鈴木健一は「作画に関しては最初から明確な完成イメージはありましたが、実際には描きながらこなれていくしかありませんでした」と当時の状況を振り返る。
また加藤は序盤の作画作業はとくに重量感にこだわったと語る。「第2話のラグビーシーンで、ジョナサンが3人の選手を引きずりながらも前進をやめないというシーンがあるんですが、ここは力強い青年に成長したジョナサンの姿を印象づける狙いがあるんです。とは言えジョナサンはあくまで人間であり、のちに吸血鬼となって人間を超越するディオとは根本的に肉体の強度が違います。つまりここでは人間としての限界も同時に示す必要があり、そのためには3人の男を背負ったときの重みをしっかりと表現しないといけない。身体のあちこちに高い荷重がかかることで生まれる「うねり」が大切で、そこはかなり細かく修正指示を出した記憶があります」(加藤)。
このように、カットごとにコンセプトを丁寧に伝えていくことでじょじょにノウハウが蓄積していき、しだいに作画は安定していった。1stシーズンから作画を担当しているアニメーター・石本峻一は「ジョジョシリーズは基本的に濃い作画が特徴で、最初は手探りでしたが、作画班のあいだではしだいに「濃さ合戦」が繰り広げられていました」と当時の作画状況を語る。
キャラクター芝居は「舞台」に近い!?
ジョジョにおけるキャラクターの芝居は、必ずしも常識に縛られない。我々は日常生活のなかで作中のような独特なポージングをすることはないし、「おまえは今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか?」といったセリフを言う機会もないのだ。ではジョジョにおけるキャラクター芝居とはなにかと言えば、それはむしろ演劇に近いという。鈴木は「舞台上のキャラクター配置や光源といったルールはありつつ、荒木先生の決めゴマの魅力を最大限に発揮するためには、ときには大きく逸脱させることもあります。突然照明を変えたりキャラクターにズバッとピンスポットを当てたり。歌舞伎でいうところの"見得"のイメージですね」と話す。このことを加藤は「舞台芝居」と表現しており、言葉は違えど同じイメージを共有していることがうかがえる。
一方で、ジョジョのバトル描写について、津田は「プロレス」と言い表している。「じつはジョジョのキャラってほとんど悩まないんです。そこはひとつのポイントで、リングに上がったプロレスラーは、なぜ自分が戦っているのかを悩んだりはしないですよね。マイクパフォーマンスや大げさなジェスチャーで、お客さんに気持ちよく分かりやすく楽しんでもらうために全力を尽くすじゃないですか。ジョジョのバトルもそれと同じで、これから自分が何をするつもりなのか、結果どうなったのかをちゃんと提示しながら戦うことで、むしろそれが旨味になるんです。アニメ的なケレン味やスピード感を優先してそこをスポイルしてしまうと、それはジョジョのバトルではなくなってしまうし、魅力も失われてしまう。プロレスに例えたのは、それが理由です」(津田)。
ジョジョにおけるバトル描写とは、長セリフのテンポや韻、アクション、キャラクター性のすべてが渾然一体となって生まれるグルーヴ感こそが醍醐味だと津田は分析しており、アニメはそれをベースに作られている。
取材・文/岡本大介
Vol. 3
疾走感と情緒感がハイレベルで両立 練りに練られた構成と演出の妙を解き明かす!
1話ごとにテーマを明確に シナリオ作業においてもっとも意識したのは、各話ごとに「何をする話」なのかを明確にしようというものだった。各話のテーマがはっきりすれば必然的に演出の方向性も決まってくる。ラインプロデューサーの笠間寿高は、そうして導き出した各話数の方向性に応じて、コメディや日常なら津田尚克、アクションは鈴木健一、ドラマ性の高い話数であれば加藤敏幸というように、ローテーションではなく演出家の個性を念頭に置きながら割り振りを実施した。その一方で、ディレクター陣はジョジョという名作を前にさまざまな思いを抱いていた。
「原作をお預りしている以上、僕らが勝手に捻じ曲げるわけにはいきませんから、何とかして荒木先生の思想を追体験しようと思っていました。ちょうどプリプロ時期に発行された『荒木飛呂彦の奇妙なホラー映画論』(集英社新書)はすごく役立ちましたね。このエピソードはこの映画が元ネタだとか、こういうことがやりたかったんだということがよく分かって、アニメの方向性もより定まったような気がします」(津田尚克)
「執筆当時の荒木先生が何を考えていたのか。当時先生が観ていた映画や聴いていた音楽などを通じて、自分なりにトレースしていきました。漫画という形ですでに成果物は世に出てはいるんですが、その奥にある気持ちを感じ取ることが、ジョジョを表現するうえで最大のミッションでした」(鈴木健一)
「原作のパワーがすごく強いですから、そこはできる限り生かしたいという気持ちがベースにありました。個人的には第4部の川尻早人が「神様 どうかこのぼくに 人殺しをさせてください」と願うシーンにグッときて、小学生にこんなことを言わせる少年漫画はほかにないだろうと感じ、ここは絶対に自分で演出したいと申し出ました」(加藤敏幸)
「第5部から参加して、過去の表現をどこまで踏襲すればいいのか、最初は戸惑いもありましたが、いざやってみたらすごく自由で。ジョジョはそれだけ器の大きな作品なんだということを改めて感じました」(木村泰大)
「第5部は絶望の中で生きる若者たちがどう生きて行くかというのが大きなテーマになっているので、『悲哀』というキーワードはつねに意識していました。自分なりに大人な部分を出そうと思っていました」(髙橋秀弥)
1stシーズンはジェットコースターからのウォータースライダー!?
制作チームは当初、原作第1部「ファントムブラッド」で1クール、原作第2部「戦闘潮流」で2クールでの構成を希望していた。しかしプロデューサーの大森啓幸はまとめて2クールで一気に放送することを要望。最終的には24話ではまとまらず26話構成となったが、これはかなり思い切った戦略だ。大森は「1部と2部をシームレスに一挙放送することで、インパクトを感じてもらえるのではと思いました。ジェットコースターに乗っていると思っていたら、いつの間にかウォータースライダーに乗っていた、みたいな(笑)」と振り返る。なかでも「ファントムブラッド」に関しては原作44話分をアニメでは9話にまとめており、これはアニメ1話あたりほぼ原作5話が入っている計算になる。
特筆すべきは、それほどのスピード感で駆け抜けながらもエピソードはほとんど割愛していないということ。これはシリーズ構成を務めた小林靖子を中心とするライター陣の努力の賜物とも言える。ともかく、この疾走感こそが多くの視聴者を惹き付け、結果として続編制作への扉を開いたことは間違いないだろう。
オリジナルシーンの追加でロードムービー感が増した2ndシーズン「スターダストクルセイダース」
スピード感を重視した1stシーズンに対し、2ndシーズン「スターダストクルセイダース」はかなり余裕をもった構成が可能となり、そのおかげで原作第3部ならではの迫力あるスタンドバトルがたっぷりと堪能できるシーズンとなった。シナリオは全体として非常に高いレベルで原作を再現しているが、随所にアニメオリジナルのシーンも追加されており、エジプトを目指して旅をする「ロードムービー感」が増しているのもポイント。
とくに第25話「「愚者(ザ・フール)」のイギーと「ゲブ神」のンドゥール その1」ではジョースター一行の6人全員で集合写真を撮るシーンが追加されている。この写真は原作第5部で承太郎が机の上に飾っていたものだが、原作中ではどのタイミングで撮影されたかは明らかになっていなかった。津田は「このタイミングしか考えられなかったので、コンテと演出を担当した鈴木さんに相談して、それで入れてもらいました」と話す。
そしてオリジナルシーンと言えばもうひとつ、第18話「太陽(サン)」も印象的だ。原作ではわずか2話で終わってしまうコメディ色の強いエピソードだが、アニメではこれを1話として構成。結果として半分以上がオリジナルシーンとなり、シナリオと絵コンテを手がけた津田の高いコメディセンスが発揮されたエピソードとなった。
構成の妙がもっとも光る3rdシーズン「ダイヤモンドは砕けない」
3rdシーズン「ダイヤモンドは砕けない」(原作第4部)はアニメシリーズを通じてもっとも大胆な構成で、それは第1話「空条承太郎! 東方仗助に会う」の冒頭からハッキリと示されている。杜王町RADIOの陽気なMCを背景に、殺人鬼による狂気の朝食シーンが映し出される恐怖。原作では物語の後半になってようやく登場するラスボス・吉良吉影の存在を示唆するとともに、平和な日常の影に潜む異常な光景という原作第4部のテーマまでを見事に表現しており、秀逸な原作の再構成と言える。
3rdシーズンでシリーズディレクターを務めた加藤は「第4部はこれまでの話とは違い、主人公が直接的にラスボスを倒して終わるのではなく、キャラクター全員が協力して倒す、もっと言えば杜王町という町そのものが吉良吉影という殺人鬼を葬り去るという構造になっているんです。それにふさわしいラストへと向かうためにも、街の雰囲気や住人たちの描写には気を配りながら積み上げていきました」と話す。また津田も「シリーズ構成的には第4部がもっともうまくいったと思います。最初から最後までひとつの街が舞台となったことと、僕らは最初から吉良吉影がラスボスだということを知っているので、そこをいい意味で使い倒すことができました」と振り返る。頻繁に流れる杜王町RADIOをはじめ、後半に登場するキャラクターが序盤にカメオ出演するといった小ネタまで、構成の妙がもっとも発揮されたシーズンとなった。
4thシーズン「黄金の風」はファン心理をくすぐるオリジナルシーンが満載
4thシーズン「黄金の風」(原作第5部)の構成でもっとも大きな点は、原作と比べてチーム戦であることがより強調されているということだ。暗殺者チームのメンバーは、原作では刺客として登場した順に名前とビジュアルが明らかになっていくが、アニメでは第10話「暗殺者(ヒットマン)チーム」にて暗殺者チーム全員の顔が判明する。さらにレストランでの食事風景を描くことで、彼らもまたジョルノたちと同じように、チームで動いていることが分かる。原作ファンのあいだでも人気の高い暗殺者チームだけに、多くのオリジナルシーンが追加されたことはファンにとっても嬉しいサービスであり、同時に4thシーズンが三つ巴の構図であることを鮮明に映し出すという意味でも効果的だ。また一方で、ミスタやアバッキオの過去エピソードが繰り上がり、フーゴの過去エピソードも追加されたことで、ジョルノ側も早い段階でチームとしての一体感が感じられる仕掛けになっている。
4thシーズンで監督を務めた木村はこの点について「暗殺者チームは原作ファンからの人気も高いですし、覚悟が決まっている人たちなのでとても魅力的なんですよね。けして独断で襲ってきているわけではないので、そこはチームとして描くことで彼らなりの信念が伝わればいいなと思いました」と語る。
そしてシリーズ屈指の名場面として名高い第28話「今にも落ちて来そうな空の下で」では、アバッキオの死に取り乱すナランチャを中心に、原作を大幅に拡張させる形でBパート全体を使って再現。絵コンテと演出を担当した監督の高橋は「このパートのラストカットでは、アバッキオが倒れている地面に一面の花を咲かせているんです。ナランチャが死んだとき、ジョルノは彼の体を植物で隠したじゃないですか。でも原作だとアバッキオに対して何かした描写はないんですね。高校生のころからそれが気になっていて(笑)。ジョルノならきっとアバッキオにも同じことをしていたのだろうと思い、最後のカットを加えました」と、名場面の裏話を語ってくれた。
取材・文/岡本大介
Vol. 4
最初に決まった主題歌は「ROUNDABOUT」
1stシーズンのEDテーマ「ROUNDABOUT」は、オリジナルの主題歌を作ろうと動いていたアニメサイドと荒木飛呂彦とのやり取りのなかで決まった楽曲だという。
音楽を担当するワーナー ブラザース ジャパンの大森啓幸プロデューサーは、当時のやり取りについて「最初はOPテーマを決めようと思って、ロックをベースにいくつかのサンプル曲を荒木先生に提案してみたんです。でも先生のイメージとは方向性が違っていて、逆にイメージに近い曲はなんですか?と伺ったところ、提示されたのがこの「ROUNDABOUT」でした。でもこういったプログレ(プログレッシブ・ロック)をオリジナル曲で作るのはかなり難しいので、それならいっそのこと「ROUNDABOUT」の使用許諾を得てそのまま使おうとなったんです」と振り返る。
その後、OPテーマよりもEDテーマのほうがふさわしいのではないかという大森の発案からEDテーマとなり、以降のEDテーマの基本路線も固まった。EDテーマは荒木飛呂彦が「執筆当時によく聴いていた曲」、あるいは「部のイメージに近い曲」というコンセプトで統一されている。
イエスの直撃世代である音響監督の岩浪美和は、「ROUNDABOUT」がEDテーマに決まったことを知って驚くと同時に、なんとか劇伴として使用できないかと考え、監督の津田尚克に「どこからでもEDを流せるようにED映像を作ってほしい」と強く提案。その結果、1stシーズンは「ROUNDABOUT」が劇伴として流れ、そのままEDテーマへと繋がっていく特殊なスタイルとなった。大森曰く「1stシーズンが終わった時、岩浪さんが僕に「楽曲の全部の箇所を入れたから」と嬉しそうに報告してくれました(笑)」とのことで、8分半もある原曲を無駄にせずに使い切る結果となった。 場面カット1
OPテーマは70年代風アニソン
オシャレな洋楽が揃ったEDテーマとは打って変わり、OPテーマは男くさい70年代風アニソンに決定。記念すべき初代OPテーマ「ジョジョ 〜その血の運命〜」を作曲したのは、ベテランアニソン作曲家の田中公平。「田中さんに依頼にいった時は「大森君、僕のところにもって来たのはね、正解だよ」って言われました(笑)」(大森)。この楽曲をきっかけとして、OPテーマは各部のテイストにマッチしたオリジナルの邦楽アニソンに定着。また正規OPテーマのほかにも、2ndシーズン「スターダストクルセイダース」では「アク役◇協奏曲」というボインゴ絡みの特殊OPテーマが制作されるなど、中毒性の高いバラエティ豊かな名曲が数多く誕生した。
またOPで大きな話題となったのが、ストーリーの進行に合わせて変化していくアニメーション。なかでも2ndシーズン第47話「DIOの世界 その3」では、ディオが「ザ・ワールド」の能力で時を止める演出が取り入れられ、衝撃を受けたファンも多かったことだろう。この仕掛けについて大森は「OP映像を担当した神風動画さんからのアイデアです。社長の水崎淳平さんがプレゼン時に「DIOなんで、9秒間止めればいいんです」って突然言い出しまして(笑)」と、神風動画による自主演出であったことを打ち明けた。
この演出をきっかけに、3rdシーズン「ダイヤモンドは砕けない」終盤には吉良吉影のバイツァ・ダストが発動してOP映像が逆再生する演出を施した「バイツァ・ダスト版OP」が作られ、さらに4thシーズン「黄金の風」ではディアボロのキング・クリムゾンの能力を描いた「Diavolo Ver.」、ジョルノのゴールド・エクスペリエンス・レクイエムの能力が描かれた「Giorno Ver.」とへと受け継がれていった。この一連のOPの特殊演出について津田は「第3部の仕掛けのおかげで、もう後戻りができなくなったんです(笑)」と苦笑い。
大森プロデューサーによる劇伴援護
本編の劇伴においても多くの専用劇伴が制作されているのがジョジョアニメの特徴。これは製作プロデューサーである大森が、音楽プロデューサーも兼任しているからこそできたことだ。「シナリオ段階から参加しているので、音楽面でもいろいろと先回りして用意することができたんです。少しでも現場への援護射撃になればいいという思いでした」(大森)。例えば大森が注力した1stシーズンの第3話「ディオとの青春」では、先行して描かれた絵コンテに合わせて専用劇伴を長回しするなど、劇場映画の制作スタイルでフィルムを盛り上げた。
なかでも話題となったのが、4thシーズン「黄金の風」第7話「セックス・ピストルズ登場 その1」で描かれた、およそ40秒にも及ぶダンスシーン。これはイタリアでのロケハン中、テンションが上がっていた木村がノリで大森に発注したもので、当然ながらこのダンスシーンの絵コンテと演出は木村が担当することとなった。「自分で発注したことすら忘れていて、こんなに長く踊るの?って(笑)。原作では4コマ程度しか描かれていないので、ほかはすべて自分で埋めないといけないんですが、僕がダンスに明るくないので、詳しい友人に原作のコマを見てもらって。どうもマイケル・ジャクソンのダンスに似ているということになり、それから1ヶ月くらい彼のライブ映像やMVなどをチェックしまくって、それでようやく出来上がりました」(木村)。
過酷なアフレコ現場のようす
キャスティングについては、知名度や人気といった要素はいっさい度外視したうえで、純粋にキャラクターに合うかどうかでオーディションを実施。津田はジョジョ声優の条件として「音圧があって上手」であることを最優先としつつ、「引き出しがあること」や「滑舌がいいこと」も加味したと言う。ジョジョの芝居は限界まで声を張るシーンも多く、「ダイヤモンドは砕けない」でシリーズディレクターを務めた加藤敏幸は「1stシーズンのときから『ジョジョ』のアフレコはとにかく大変です。つねに最大級の熱量と声量を要求せざるを得ず、このあとにもう1本収録があったらどうするんだろうと、勝手ながらこちらが心配になってしまうほど。キャストの皆さんにはいつも「ごめんなさい」って思っていました」と、アフレコのようすを振り返る。
しかしそんな過酷な現場であるにも関わらず、オーディションにはたくさんのジョジョ好きなキャストが集まり、必然的にブース内にはジョジョ好きなキャストたちが増えていった。初参加で戸惑うキャストに対して「ジョジョのセリフは小さな"ッ"も読むんです」など、率先してレクチャーする光景も見られたという。笠間寿高プロデューサーは「原作のセリフ回しを一言一句変えずにやるというのが当初のテーマだったので、スタッフサイドとしてはとても助かりました」と、キャスト陣への感謝を口にする。実際、有名な花京院典明の「レロレロ」も、しっかり17回で収録されている(第9話「黄の節制(イエローテンパランス)」)。
「スターダストクルセイダース」のシリーズディレクターを務めた鈴木健一は、初収録のためスタジオへやってきた花京院役の平川大輔に「今からレロレロを練習しておいて」と最初に頼んでいたというから、そのこだわりは半端なものではない。もちろん、これらのオーダーにパーフェクトな芝居で返すキャスト陣もまた、ジョジョ愛で溢れているといえよう。
コマ単位での最終調整で、最高のリズム感を演出
「スターダストクルセイダース」以降の試みとして、再カッティングという手法も取り入れている。これは最初のカッティングで30秒ほど余裕を持たせた編集でアフレコに臨み、その後セリフとセリフの間にあるわずか数コマを細かくカットしていきながら最終調整をするというもの。これによりさらに気持ちの良いリズム感を出すことができ、長セリフの多いシーンでもダレることがないテンポを作り出すことができる。こうしたじつに細かい創意工夫の積み重ねが、ジョジョらしい気持ち良さに繋がっているのかもしれない。
「ジョジョアニメ」とは、なんだったのか?
計4回に及んだプロダクションノートはいかがだっただろうか? 企画、シナリオ、映像、音響のすべてのセクションにおいて、強い原作愛とこだわりに溢れた現場であったことがお伝えできたのではないかと思う。さて最後に、「ジョジョアニメ」とはなんだったのか? について触れてみたい。
本稿を執筆するにあたり、今回改めてプロデューサー&ディレクター陣へ取材を行なったが、ジョジョの話になると誰もが一瞬にして少年のような顔付きに戻っていくのがとても印象的だった。アニメーション制作を取り巻く環境や現場は、我々が想像する以上にハードで過酷なもの。約10年近くにも渡り作り上げたその舞台裏では、きっとさまざまな苦悩や人間ドラマが起こったに違いない。それでもなお、ジョジョの話となると一気に少年の顔に戻ってしまうところがジョジョチームのスゴさであり、この顔付きこそが「ジョジョアニメ」のすべてを物語っているように感じた。
最後に、今回取材を行ったスタッフ陣に「自分にとってジョジョアニメとは?」という質問をぶつけてみた。その返答はさまざまだが、なんとも言えぬ"清々しさ"に満ちたものだったので、ここに記しておきたい。
─ 津田尚克 「未熟だった僕に、演出家として必要なもののすべてを教えてもらった作品です」
─ 鈴木健一 「僕の人生を助けてくれた作品。キャリアのうえでも確実にターニングポイントになりました」
─ 加藤敏幸 「演出の視野を広げてくれました。面白ければ、迫力があればなんでもアリなんだと吹っ切れました」
─ 木村泰大 「作っているときは辛くて、終わると寂しい。そんな珍しい作品ですね」
─ 髙橋秀弥 「ジョジョを作った3年間はとても得難い体験で、僕の人生の宝物になりました」
─ 大森啓幸プロデューサー 「長い戦いになると予感していたので、何があっても諦めないことだけは心に誓いました」
─ 笠間寿高プロデューサー 「2ndシーズンが終わった時、スタッフ全員で肩を抱き合いながらわんわん泣いたことを今でも鮮明に覚えています」
- 取材・文/岡本大介