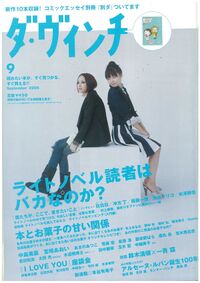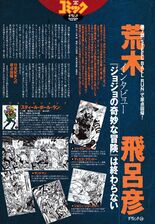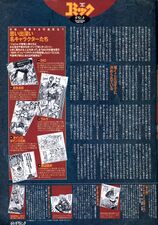Da Vinci (August 2005)
Quarterly S (June 2005)
Interview Archive
An interview with Hirohiko Araki at his house, published in the September 2005 issue of Da Vinci magazine.[1]
Interview
第7部『STEEL BALL RUN』で原点回帰!
荒木 飛呂彦
インタビュー
『ジョジョの奇妙な冒険』は終わらない
1986年から『週刊少年ジャンプ』で連載がはじまった
超大河コミック『ジョジョの奇妙な冒険』の「第7部」
『スティール・ボール・ラン』が、現在『ウルトラジャンプ』に
連載の場を移し、ジョジョの血筋と運命の物語は今も続いている。
しかし、設定が19世紀末と「第1部」と時代が重なっている。
もちろん、ジョジョもディオもスタンド能力も登場する。
これはパラレルワールドなのか、それとも血筋の原点回帰か?
「集大成を意識した」という『SBR』はダイナミックな
躍動感にあふれ早くも大傑作になりそうな予感に満ちている!
取材・文/大寺明 撮影/川口宗道 ©荒木飛呂彦/集英社
運命に魅入られた血筋を描く『ジョジョの奇妙な冒険』(以下『ジョジョ』)の連載が今なお続いていることをご存知だろうか? 1986年から連載がはじまり、第6話『ストーンオーシャン』まで『ジョジョの奇妙な冒険』というタイトルで描き続けられてきた。しかし、ここへ来て『ジョジョ』シリーズは新たな局面を迎えている。
まずタイトルが『スティール・ボール・ラン』(以下『SBR』)となった。そして時代設定が連載開始時の第1部と同じく19世紀末となっているのだ。これは第6部の驚愕のラストでパラレルワールドへ突入したことにより時が一巡し、またゼロから始まった、ということなのだろうか。あるいはこの物語がループ状にジョースター家の物語につながっていくのだろうか。
その新たな世界ではジョジョもディオも登場するし、ツェペリ(第1部ではツェペリ男爵というキャラが登場)が準主役だったりと、馴じみ深い名前が再登場する。そして連載の場が『少年ジャンプ』から月刊誌『ウルトラジャンプ』へと移った。『SBR』はさまざまな面で『ジョジョ』シリーズの区切り目となっているかの観があるのだ。
これまでコミックスの巻頭にあった家系図は『SBR』からはなくなったが、物語は依然、ジョジョの物語となっている。『ジョジョ』シリーズの新たな展開に作者の荒木飛呂彦さんは何を意識しただろう?
ひとつ、確実にわかることは、『ジョジョ』を「終わらせない」という明確な意志である。
まるで『ジョジョ』で描かれる世界観を実体化したかのような西洋風のご自宅で、大理石の円卓を囲みインタビューははじまった。館の主はまるで少年のように快活でエネルギッシュだ。
まず、第7部『SBR』で舞台を再び19世紀末に戻した真意をうかがってみた。
「原点に戻ってみようかな、という感じがあったんです。サスペンスや人間ドラマがはっきり見えるようにスタンド能力もあえてシンプルにしました。これまで『ジョジョ』を読んでなかった読者も意識したいと思ったんです。いきなりスタンド(視覚化された超能力)を出すのではなく、ゼロからでもわかるように展開していきたい。
時代をまた19世紀末に戻したのは、自分の作品への集大成の意味があるのかもしれない。ただし、パラレルワールド的な意味合いでこの世界でも因縁は重なっていて、やはりジョニィ・ジョースターのライバルはディオだったり、そういう象徴的なものは意識して描いています。これまで『ジョジョ』を読んできた人にはわかるようにね」
『SBR』では北米大陸を乗馬で横断する壮大なレースが描かれる。野性味溢れるダイナミックな「冒険」に再び戻った観があり、今後の展開が楽しみになる作品だ。この『SBR』で描かれる砂漠を馬で走る男のイメージは、荒木さんにとって特別な思い入れがあるのだという。
「子どもの頃に父に連れられていちばん最初に観た映画が、クリント・イーストウッドの『夕陽のガンマン』で、僕の原点なんです。ストーリーはぜんぜんわからなかったけど、孤独な男が砂漠で馬に乗っているイメージが強烈に脳裏に焼きついている。『SBR』を描くにあたってあらためて見返したんですけど、神話のような象徴的な描かれ方をしてるんですよね」
また、19世紀末という時代は、人類の歴史の中でも極めて特殊なターニング・ポイントの時代ではないかと荒木さんはいう。
「ルネッサンス時代に匹敵する“はじまりの時代”っていう感じがあるんですよね。アメリカでは電話機が発明されて一挙に普及したり、美術ではフランスで後期印象派やピカソが出てきたり、日本では明治維新が起こったり、世界中に巨大なひとつの流れがあったと思う。人口も爆発的に増えた時代なんです。いろんなもののルーツがその時代にはあって、人間が先祖代々受け継いでいる因縁も、この時代に“はじまり”として凝縮されている気がするんですよね」
まるで限界まで膨張した宇宙が収縮に向かい、再びビッグバンを起こしたかのような展開である。ひとつひとつの物語はサスペンスや戦いのかけ引きが中心だが、『ジョジョ』シリーズ全体を見渡したとき、その壮大な構想は最新宇宙論かインド哲学でも読んでいる気分にさせる。
『ジョジョ』の根底にある「因縁」そして「運命」というテーマ。『SBR』でパラレルワールドに入ったことで、今後この「運命」というテーマが、これまでのように血筋としてではなく、違う様相で浮かび上がってくるように思う。荒木さんの描こうとする「運命観」をうかがった。
「先祖からの因縁を受け入れて、立ち向かうっていうのが『ジョジョ』のテーマなんです。うじうじと自分の運命を呪ったり、運命を変えようとするんじゃなくて、それを超えていこうとする姿を描きたかったんです」
たとえ運命に翻弄されようと、運命を肯定し覚悟する者が描かれ続けてきた『ジョジョ』を読むと、いつも背筋がぴんと伸びるような気分になる。たとえそれが悪役であっても、みな何かしら自分なりの生き方や哲学を持ち、運命に抗する強い精神力を持っていると感じさせるのだ。
「第4部に登場する吉良吉影という殺人鬼なんて、今の精神医学から言うと、たぶん親から虐待とか受けてああいう性格になってしまった被害者なのかもしれない。でも、悪役をそういうふうには描きたくないんです。確かに人殺しなんだけど、そういう自分を肯定して自分なりの理論を持って生きている」
強さ、という観点からすると、そうしたキャラのほうが強く怖いと感じると荒木さんはいう。単純な善悪に捉われない「強さ」を荒木さんは描いているのだ。
「精神的にマイナス方向に行かないのが少年マンガの基本なんです。たとえば、なんでサイボーグになってしまったんだろう……とくよくよするようなマンガはあんまり好きじゃなかった。なんかスカッとしねえなぁっていう。その宿命を利用して生きていけばいいのに、と思ってたんです。闘うにしても、二人が激突して両者の精神が上へ上へとどんどん成長していく闘いを描きたかったんです」
『ジョジョ』に登場するキャラクターたちはみな魅力的だ。ディオや吉良吉影といった悪役もみな自分なりの信念やルールを持って生きている。では、荒木さんがマンガを描く際のルールとはどういったものだろう?
「僕の中のルールはあくまでも人間、なんです。強力なメカや剣を手に入れて敵を倒したりはしない。あくまでも自分の精神力や肉体の力で勝つ。ただし、根性というのはあまり信用してないんです。急に力が出て勝敗をひっくり返すにしても、そこに理論がないと自分で納得できない。あとは、マイナス思考にならないこと。悪役も人間らしい人も自分の生きる道については肯定しているんです」
それが『ジョジョ』最大のテーマ“人間賛歌”なのだろう。たとえ運命が変えられないとしても、そこで挫けずに肯定して生きる。『ジョジョ』に感じる真っ直ぐな精神性は、この揺るぎないテーマがあるからだろう。
それにしても、連載当初から読んできたが、まさか累計85巻まで続くとは想像もしていなかった。あらためて振り返り、ここまで続いたことを荒木さんはどう思われるだろう? 第1部から第7話『SBR』に至る変化を聞いてみた。
「『ジョジョ』というタイトルになったのは、その頃、ファミレスのジョナサンをよく打ち合わせに使っていたからなんです。最初はお爺さんと孫という関係を意識してましたね。その頃、小説の『エデンの東』や映画の『ゴッドファーザー』にすごい感動して、自分もそういう作品を描きたいと思ったんです。
連載当初は『北斗の拳』やシュワルツネッガーの映画が流行っていて、その影響で肉体追求の話だった。第2部もまだその延長です。でも、肉体的な闘いを描いていくうちに、心なんだな、とわかってきて、精神的な闘いに移っていったんです」
そして、第3部からは本格的に精神と知恵の駆け引きが勝負の鍵を握る「スタンド」が登場する。このスタンドの登場により、マッチョな格闘マンガの図式を抜け出し、オインゴ・ボインゴや岸辺露伴といった非肉体的とでも言うべき数々の名キャラクターが生み出されていった。
「三代にわたるディオとの因縁に決着がつく第3部で実は完結するつもりだったんです。でも、第3部はロードムービーのような物語だったので、襲ってくるタイプのスタンドばかりで、蜘蛛の巣のように持つタイプのスタンドのアイデアが使えなかったんです。そういうスタンドのアイデアがいっぱい余っていたので、設定を街ということにして第4部をはじめたんです」
第4部では架空の街・杜王町が舞台となる。綿密な街の地図を作成し、店の名前まで決め、登場キャラが街に実在するかのように徹底して配置にこだわったという。そこに「日常」を描きたかったと荒木さんはいう。
「杜王町は僕の生まれた仙台をイメージしているんですが、僕が子どもの頃はまだ野山に囲まれていた。でも、80年代のバブル期に山が切り崩されてベッドタウンができてきたんです。寺町が潰されたりもしていて、宗教上いいのかな、と思ったりしましたね。奇麗な家やマンションがいっぱい建ってるんですけど、住んでる人たちは全員よそ者で、昔からの住人から見ると、ちょっと不気味だったんです。幽霊が出る噂がいっぱいあったりする。そういう話を聞くと、裏に何かあるのかなと想像しちゃって、それが杜王町のイメージになってるんです」
そして第5部では舞台を荒木さんが15回以上も旅行したというイタリアに移し、ギャングたちの集団劇を描き、第6部では初の女性主人公を描いていった。ここまでくると、もはや『ジョジョ』を描き続けることが荒木さんの運命であったかのような奇妙な感慨に包まれる。
「第6部で時代設定が2011年という近未来になったのは、第3部を描いていた頃がもう現代と重なってましたから、もうしょうがなかったですね。超未来は描きたくないんです。やっぱり現代の自動車とかが走っている感じが欲しいんです」
そして『SBR』は再び原点に戻り19世紀末からスタート。自在な表現が許されるマンガの特性を最大限に生かし、荒木さんは時間すら超えてしまった。
「ここまで続くとは自分でも思ってなかったけど、『ジョジョ』で描いているテーマは追っていくだろうな、とは思ってました。運命を感じるし、あっという間でした。どんな作家でも代表作は一つか二つだと思うんです。手塚治虫先生でもひとつの流れとして読むと、すべての作品のテーマが続いている感じがする。短編小説が集まって大きな河になっているようなイメージのマンガを僕も意識しています」
『ジョジョ』シリーズで荒木さんが最初にこだわった「祖父と孫」という関係。それは荒木さん自身が「お爺ちゃん子だった」という影響があるらしい。どんな少年時代だったのだろうか?
「妹が双子なんです。親の愛情は平等なのかもしれないけど、双子って同じ時間に起きて学校に行って、同じ服を着たりしてるわけだから、どうしても自分だけが離れている感じがあって、お爺ちゃんの所にばかり遊びに行ってたんです。そこでマンガや映画や芸術に触れて孤独を癒されたんですよね。お爺ちゃんは模型を作ってくれたり凧を作ってくれたり、何かを作ることがとにかく好きな人でしたね」
そうした少年時代に荒木さんはマンガを描きはじめた。きっと作ることが好きなお爺ちゃんの影響があったのだろう。また、荒木さんがもっとも影響を受けた人物に画家のゴーギャンがいる。それは表現のみならず、生き方にも影響を与えた。
「絵を描くためだけにタヒチの無人島みたいな所で暮らすというのを聞いたとき、そこまで芸術って凄いのかって衝撃を受けて、物事の捉え方が変わったんです。より深く裏側まで見るようになった。器用にいろんな分野を描く人もいますけど、ゴーギャンの生き方を知って、僕も何かひとつのことを追っていきたい、と思うようになった」
それが荒木さんにとって『ジョジョ』というひとつの長大な物語を描き続けることにつながっていったのだろう。劇的な変化がない限り、荒木さんは『ジョジョ』を生涯描き続けていくつもりだと話してくれた。
荒木さんがストーリーを考える際、街の地図や部屋の見取り図を綿密に作ることからはじめるという。さらに重要なキャラクターに関しては親の略歴まで含む履歴書を作成する。さらに舞台が海外であれば実際に取材旅行をし、街の雰囲気だけでなく道の位置や距離感まで把握してから描きはじめるという。
「主人公が地球のどこにいるのかわかっていたいんです。地球の緯度経度のどこらへんにいて、周りに何があるのかをわかってないと、登場人物がどういうふうに行動するのか、わからなくなるんですよね」
そう笑って話すが、『ジョジョ』の奥深さをあらためて感じる。あたかも本当にその世界で息をしているように登場人物個々の自我まで感じさせてしまうのが『ジョジョ』の魅力である。そして荒木さんはさらに面白い話を聞かせてくれた。
「彫刻家のミケランジェロが、石を見ただけですでに削る形は決まっているって話しているんです。その話を聞いて、なんでも彫れるはずなのに、その形しか彫れないというのは、運命だと感じたんですよね」 マンガを描いていても同じことを荒木さんは感じるという。
「たとえば主人公が今青山にいて次にどこへ行こうかってなったとき、電車で新宿にも東京にも名古屋にも行けるのに、性格を決めると選択肢が無数にあるにもかかわらず新宿にしか行かなくなるんです。作者にもどうしようもない。無理にストーリー上都合のいいほうに持っていこうとすると、辻褄が合わなくなって破綻してしまう。描いていてそこに運命を感じる。ミケランジェロの言っている意味がマンガを描いていてわかるんです」
なんでも描けるはずなのにすでに決まっている。『ジョジョ』に描かれる運命の奇妙さ、崇高さとは、作者にすらコントロールしかねるものなのかもしれない。だからこれだけマンガ史の中でも突出した物語を描けた(描かされた)、という言い方もできるのではないだろうか。とてつもない領域で荒木さんはマンガを描いている。そんな荒木さんがマンガを描いていて、もっとも盛り上がる瞬間とはどんなときなのだろう?
「やっぱり誰もやったことがないことを描くときがいちばん楽しい。もうそれは人気とか関係ないんです。みんな引いてもいいくらいの感じなんです」
何かとんでもないものが描かれつつあるという予感が『SBR』には、たしかにある。