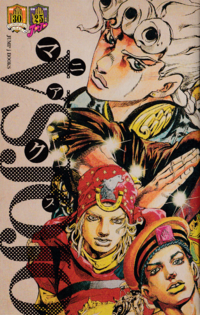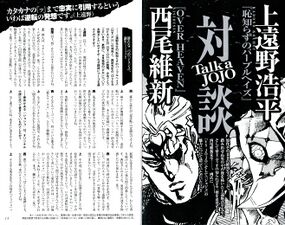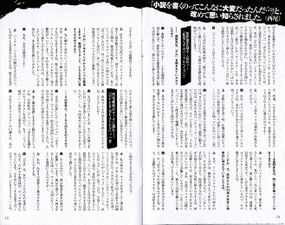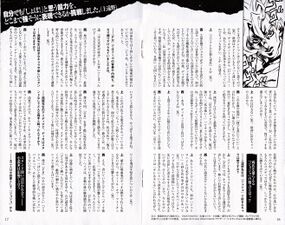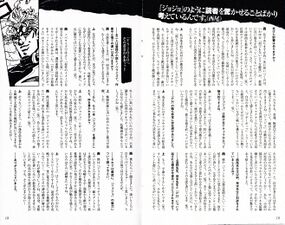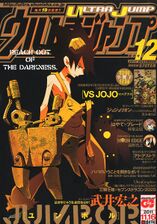VS JOJO Maniacs - Ultra Jump (November 2011)
Sekibenren Goes (November 2011)
Famitsu (July 2012)
Interview with Kouhei Kadono (author of Purple Haze Feedback) and Nisio Isin (author of Over Heaven), published in the "VS JOJO Maniacs" booklet. Included with the December 2011 issue of Ultra Jump released on November 19, 2011.[1]
Interview
"Why did you choose Fugo as the subject for the novel?"
When it came to the subject matter, anything was allowed. I figured I could do basically anything within the "JoJo" universe. That said, writing a novel about Fugo was just really convenient for me. There were other candidates, but this was a story I just had to write.
"What were the other candidates?"
For example, where exactly did Stroheim die in Stalingrad? (laughs) The thought always entertained me, though I wonder if it's something readers would enjoy as well.
This other idea is a bit odd, but instead of directly competing with Araki-sensei, I wanted to try a "Futaro Yamada" style JoJo story. For Part 5, perhaps you could call it "Italian Ninja Scrolls".
"Much like the villains in JoJo, the ones in Purple Haze Feedback have a very powerful presence."
Araki-sensei drew the characters and Stands, but it gave me the most peculiar feeling. After seeing his material, I couldn't help thinking, "Did I write this?" That is, even though I had come up with the characters and Stands myself, I got a sense that they weren't really mine at all... I suppose this is the power of the original work. The novel also goes into further detail on their visuals, but I was surprised and delighted by how well Araki-sensei picked up on them.
新たな二つの『ジョジョ』、誕生——ッッ!!
——上遠野先生の『恥知らずのパープルヘイズ』(以下『PH』)の発売と、西尾先生の『OVER HEAVEN』(以下『OH』)の脱稿、おめでとうございます。最初に、9月発売の『PH』についてお聞きしたいのですが...なぜ題材にフーゴを選んだのですか?
上遠野 (以下、上) 題材は何でも良かったんです。『ジョジョ』の世界なら何でもできると思っていたので。ただ、フーゴだと小説にする面で、本当に都合が好かったんです。他にもいくつか候補はありましたが...これは書いても仕方ないネタばかりだったので。
西尾 (以下、西) そちらのネタも知りたいですね。
上 例えば、スターリングラードでシュトロハイムが死ぬところとか (笑)。こんなの自分が 楽しいだけなので、読者が望んでいるものかどうか...。そして変な話ですけど、直球で荒木先生に真正面から勝負を挑むのではなく、『ジョジョ』を使って山田風太郎 (※注1) のような物語をやってみようという考えもあったんです。5部で「イタリアン忍法帖」というか。
西 確かに流れが『忍法帖』の雰囲気ですよね。
上 両チームが個別に対戦するという、忍法帖のフォーマットにのっとって展開させているんですよ。いわゆる「ジャンプ」的な見せ方です(笑)。あとは単純に、漫画本編にフーゴのその後が描かれていないからです。
西 荒木先生は文庫本の後書きで「フーゴは裏切り者として使うつもりだったけれど、子供たちが読む少年漫画という中で、そういった人物は描けない」...みたいな内容のことをおっしゃっていましたよね。
上 実際に小説を書いてみて、殺伐としてしまうので少年漫画にはならないと感じました。
西 そもそもフーゴって、持っている能力も「殺人ウィルス」とか、ひどく物騒ですし。
上 もう少しバイオレンスに寛容な、それこそ'70~'80年代だったらありかもしれないですけどね。
——原作がある『ジョジョ』は、オリジナル小説に比べて書きにくいものでしたか?
上 全く逆でしたね。あまりに書きやすくて、展開に詰まることもほとんどなく、むしろ書き続けたせいで体力面で消耗したくらいです。西尾さんのような、異常な筆の速さを体感したかも知れません (笑)。
西 僕は逆に今回はなかなか書けず、大変でした。だからスラッとかける上遠野さんはすごいです。『ジョジョ』の登場人物ってクセがあるので、文章にするとなかなかうまく表現できないんですよ。
上 その辺、私は完全に反則で書きましたね。原作の色々な台詞やシーンを引用して、そのまま文章にしていました。カタカナの「ッ」まで忠実に引用するという、いわば逆転の発想です。だから西尾さんのいう「『ジョジョ』っぽさ」という面では苦労はありませんでした。そして書いていて発見したのは、「ッ」は地の文ではほとんど使わず、台詞だけにした方が『ジョジョ』っぽさが引き立つんです。あと「じゃあねーよ」とか、「あ」を必ず入れるとか、本当、細かいところばかり(笑)。
西 頭で『ジョジョ』っぽくしようと意識しても、なかなか紙一重のテイストなんですよね。
上 そもそも荒木先生ご自身が「ジョジョ」っぽさを意識されているわけではないでしょうから。荒木先生のテンションが、そのまま『ジョジョ』っぽさになっているというか。あと読者はあまり気付かないかも知れませんが、実は『PH』では本文に「スタンド」という言葉は一切出していないんですよ。そしてそれを補足するために、わざわざ合間にスタンド解説を入れたりして。そもそもこの作品って「能力」とか「ウィルス」とか、本来は説明しなければならないものがいっぱいあるんですけど…敢えて「スタンドとは!?」的な説明はしないと決めたんです。
西 『ジョジョ』とはそういうものだ、と。
上 この辺は山田風太郎と一緒ですね。「忍法」と頭につけたら、大抵の不思議な技も説明がついてしまう。
原作愛を抱き…読めッ!『恥知らずのパープルヘイズ』!!
——西尾先生、『PH』を読まれていかがでしたか?
西 素晴らしかったです! しかも題材の5部に限らず、原作の色んな要素が本文中に散りばめられていて、読んでいて楽しくなります。普通、いきなりあのスタンドが出るなんて思わないじゃないですか。登場させるスタンドはどのように選んだのですか?
上 …いや、5部キャラは選択の余地がなかったので。
西 ああ、そういえばほとんど死んでいるんですよね。あのかたやあのかたが幸運で生き残っているくらいで。
上 実際に小説を書く時、序盤の説明にちょうどいい原作の敵キャラが欲しいと思ったら…こいつくらいしか残っていなかった! (笑)
西 そしてそんな数少ない生き残りが、『PH』では、さらにひどいめに…。あと、最初に刺さったのは「少年の名はパンナコッタ・フーゴ」という部分です。そういえばこいつ、こんな変な名前だったっけって (笑)。しかもその変な名前から逃げるのではなく、おばあちゃんに「パニー」と呼ばせて強調していたりして。まずそこがいきなり面白かったですね。
上 多分イタリア人にとってはそんなに変な名前じゃないのかも…と自分に言い聞かせて、あえてそのまま流しています。
——上遠野先生は、特に筆が乗ったシーンはありますか?
上 やっぱりバトルシーンかなぁ。筆が乗ったというか、集中して一気に書いてどっと疲れた感じです。逆に難しかったのは、漫画を引用する部分です。しかも途中でさりげなくオリジナルシーンに移行しているので、その繋ぎに苦心しましたね。
——『PH』は、原作からの引用が非常に効果的に使われていましたよね。
上 まず、フーゴとジョルノたちの別れのシーンだけは、絶対に入れようと決めていました。それがないと始まらない。…しかしいざ引用してみると、原作通りなのにジョルノが小説だと少し不気味に映るんですよね。妙に冷静というか、何を考えているのか分からないというか。まあ、小説でジョルノは既にボスとして君臨しているので、「これくらい怖いだろう」…と、敢えて台詞も減らして怖さを印象づけようと書いています。
西 こうして小説での貫禄を目の当りにすると、やっぱりディオの息子なんですよね。あと、上遠野さんはブチャラティはお好きなんですか?『PH』で結構出ていますが。
上 好きなのは当然ですが、ブチャラティを出すと話が締まるんです。彼のような真っ直ぐな人物は、物語を明確にしてくれる。私にとってブチャラティの5部への関わり方は、「真っ直ぐだけど、真っ直ぐになれない人物がジョルノと出会い、真っ直ぐであることを再確認する」というものだと解釈しています。
——『PH』ではオリジナルスタンドも登場しますが、物語とスタンド、どちらを先に考えられたのですか?
上 先に細かく決めていったのはスタンドですが、そもそもスタンドって戦いの内容を表すものでもありますよね。特に今回は主役がパープル・ヘイズなので、バトルだと一発で勝負がついてしまう。それをどこまで敵スタンドで盛り上げることができるのか、と工夫したつもりです。そしてパープル・ヘイズ自身にも、ある変化を描いてみました。
西 ああ、あれは最高でした!
上 パープル・ヘイズの強力すぎる力って、いわばキレる若者なんですよね。周りを見ずにキレると誰も話を聞いてくれないけど、ちょっと身を引くと解決策だって生まれる…そんな印象から思いついた変化なんです。
西尾維新がディオに挑む——『OVER HEAVEN』ッッ!!!!
上 西尾さんも作品を書き終えたんですよね。どうでしたか?
西 先ほども言いましたが、すごい苦戦しましたね。「小説を書くのってこんなに大変だったんだ…」と、今回改めて思い知らされました。
——その苦労は、どこから出たものですか?
西 先ほどお話しした『ジョジョ』っぽさ…それこそ『ジョジョ』的な台詞回しですね。自分で同じようなものを書こうとしたら、ただの品のない台詞になってしまうんです。
上 書く側が意識しすぎると駄目なんでしょうね。今回私は『ジョジョ』っぽさを意識せずにキャラクターを決めて、もう「こういう奴だ!」と決めきって書きました。
西 それでもキャラクターの口調とか、気にし始めるときりがなかったです。
上 私の場合は、キャラが多少くどく喋る程度ですね。それこそ台詞で同じ単語を3回繰り返させたり。そのせいで担当に「この台詞ってくどくないですか?」とかチェックされて。「くどいのが『ジョジョ』なんだ!」と、直しませんでしたが (笑)。ただ、小説としてのリズム感は、普段の自分の作品と変えていません。というか、少なくとも自分はそんな器用なことはできない。劇中をそのまま引用した箇所は荒木先生のリズムになっているので、そこで自分と荒木先生のリズムの違いを改めて感じました。
西 そんなわけで、僕は物語を基本は地の文で展開しています。僕は6部でプッチ神父が少しだけ語った、ディオの「天国に行くノート」を題材にしたのですが…。
上 ああ、あまりの邪悪さに燃やされたというノートですよね。
西 『OH』は、あのノートそのものを書いたんです。だから小説自体が、ディオの語りになっています。さすがにディオも文章では「~だゼェーッ!」とか「URYYYY!」とか、そこまでテンションは上がらないと思うので (笑)。最初はタイトルでもちょっと迷いましたね。ディオのノートだから『Dノート』...とか。あちらでもお仕事させてもらっているのでちょっとまずい、とか (※注2)。
上 『エジプトDD殺人事件』とか (笑)。
西 3部序盤でジョセフがディオを念写した時に語る「こいつは世界のどこかに潜んで、何かをたくらんでいる」という台詞があるんですけど...そんな曖昧な理由で彼らはディオを倒そうとしていたんですよね。その後、ディオを倒すのはホリィを助けるためという理由が固定されましたが、スタンド使いを集めて何をしようとしていたのか、ディオの目的は明かされていないんです。一応「世界の頂点に立つ」とありますが、明確な目標は本編中には語られていない...そう思っていたら、6部に「天国へ行きたい」と書かれていて。ディオが何を考えていたのか書いてみようと思ったんです...が、これはこれで、やってみるとすごい苦労で。何でディオを選んでしまったのか!
上 それは仕方ない (笑)。最初に決めちゃったんだから。
西 この企画の最初に「何でも書いていい」と言われたから、つい選んでしまったんですよ。作中で一番好きなキャラですし、ラスボスとして相当なカリスマを持っていましたから。
上 西尾さんはとにかく最強キャラが大好きですよね。『めだかボックス』を読んでも「俺は強い!」「私は強い!」ってキャラが多くて。今回の企画でそのスタイルを一貫した感じですね。...でもディオって結構負けていない? その辺は最強キャラ好きとしてどうなんですか?
西 …本当、ディオって意外と負けっぱなしなんですよね (笑)。
上 1部でジョナサンに殴られて泣いたりして。
西 この人は負けてばかりでずっと目的を達成できないでいるのに、なぜ己を「帝王」と位置づけし続けられたのか、心の迷いはなかったのか。その辺りに興味をそそられます。もちろんコメディではなく、しっかりシリアスに掘り下げています (笑)。
両氏を捕らえる『ジョジョ』の魅力とはッ!?
——上遠野先生は「ジョジョ』で好きなキャラは誰ですか?
上 メインもサブキャラも全部好きですね。だから『PH』では、キャラをランクで選ばずに出しています。勢いで石仮面まで出したけど、アレは昔からのファンしか分からないという。
西 今の若い読者はピンとこないかも知れませんよね。
上 あとシュトロハイムも、何か「シュトロハイムは必ず名前を出さないといけい!」と妙な決め事が自分の中にあって (笑)。だから主役にしたフーゴやパープル・ヘイズも決して特別扱いというのではなく、先にお話した書きやすさによる起用が大いですね。そしてその一方で、キレやすい若者を書きたいという欲求もあったんです。フーゴは「キレるキレる」と言われながら、実は原作では1回しかキレた場面が描かれていないので、「じゃあ、もっとキレさせてみよう」と。
——『PH』ではフーゴの背景や内面も、かなり掘り下げられていましたよね。
上 「実は実家が成金」とか書いてしまったけど...大丈夫なんですかね?
西 地の文でフーゴの過程を説明して、最後に台詞で「なんとしても貴族になるッ!」とか、とても『ジョジョ』っぽく感じました。そもそも荒木先生による人物背景の掘り下げって、エモーションを補強するためという印象がありますよね。僕もディオを、もっと野心的にしても良かったのかなぁ...?まぁ、まだゲラがあるのでギリギリまで調整します (笑)。
——西尾先生は好きなキャラや欲しいスタンドはありますか?
西 ミーハーがバレないように、考えて発言しないと (笑)。...大体こういう話だと岸辺露伴のヘブンズ・ドアーになります。あとトニオさんのパール・ジャムとか。こういう欲しいスタンド話になると、やっぱり4部ですね。
上 これだけ色々な能力がそろっているのも、荒木先生って「ちょっと弱くない?」と思える能力を、面白く拡大するのが驚くほど上手いからなんですよね。私は今作で「他人が過去に話した陰口が分かる」能力とか、自分でも「しょぼ!」と思う能力を、どこまで強そうに表現できるか挑戦しました。
西 僕は今回、『OH』を書く際に原作を改めて読んでみたんですけど、まずディオって復活した時はスタンドを持っていなかったんですよね。後に弓と矢で目覚めるまで。そんな状況でスタンド使いと戦えるのかと思ったら...実は意外と勝てるんですよ。スタンドはスタンドでしか倒せないけど、冷凍法とか目からビームとかで、スタンド使いは倒せる (笑)。
——西尾先生のアイディアで、ディオはスタンドなしでどんな相手と戦ったんですか?
西 没案ですけど、ホウィール・オブ・フォーチュンっていたじゃないですか、あの車の男の。ディオはあいつに目からビームで勝っちゃうという話を考えていました。で、奴はディオの技を見て、承太郎たちに使ったガソリンを飛ばす技を思いついたとか (笑)。
上 確かに吸血鬼のディオは燃やされても死なないから、ホウィール・オブ・フォーチュンごときでは勝ちようがない (笑)。
西 ええ。書いているとどんどん「ディオ強すぎる!」ってなって展開が難しくなっていく。...一応加えておきますと、ちゃんとシリアスに書いていますからね?『PH』のパープル・ヘイズは、苦戦の後の勝利描写が圧倒的でした。
上 冷静に検証していくと、実は意外と危うい部分があるかも知れません。ただ読者には「どうやって勝つんだろう」と常に思って頂くために、敵役の細かい描写や小説のテクニックで盛り上げています。
西 僕は『PH』のその部分がすごい『ジョジョ』っぽいと感じました。『ジョジョ』のバトルって、それこそ絶望的な戦いばかりじゃないですか。
スタンド使いは引かれ合う——小説家は影響し合う
——お二人は小説家として『ジョジョ』から受けた影響はありますか?
西 色々ありますが真っ先に思いつくのは、いわゆる「何でもないような敵役」が、最強に近い能力を持っていてもいいんだ!...ということです。その一方で、ラスボスのディオは時間を数秒止めるだけだったり (笑)。仗助のクレイジー・ダイヤモンドも最初、「これが少年漫画の主人公の能力でいいのだろうか?」と思いましたね。でもあの能力こそが最高だった!...つまり一見使いにくそうな能力でも、どんどん物語で価値を持たせたり、その逆もできたり。『ジョジョ』のそういう意外性が好きです。本を読むときは驚かされたい、と思うんですけれど、ジョジョは期待以上に驚かせてくれる。だから僕は小説を書くとき、あるいは漫画原作を書くとき、『ジョジョ』のように読者を驚かせることばかり考えているんです。
上 私は基本的には対立の構造の作り方ですね。「彼らはどうして対立しているのか?」とか。1部はそれが特に顕著で、ジョナサンもディオもそれぞれ対立する理由を抱いている。主人公側から見ると敵は悪ですが、敵は敵で真剣に生きていて、ちゃんと戦う理由が存在する。だから下手をすると敵が勝つこともあったりする。普通、物語はどこか主人公に都合よくできていて、敵はやられるために出てきますよね。「ジョジョ』は敵が真面目だから、主人公も真面目でなければならない。そういったキャラクターたちの必死さは大切にしたいと感じましたね。...とか言っていると、自分の書く『ブギーポップ』シリーズでも敵役ばっかりが目立って、「主人公に勝てない」とかいいながら戦いを挑むようになってしまって (笑)。
——「ジョジョ』は敵が全てキャラが立って魅力的ですよね。
上 だからこそ、やっぱり正義を描くことは大切なんだとも思いました。特にノワール系の作品とか、皆悪人ばかりで悪合戦をしがちです。でも「俺が正義だ」と主張しあってくれないと盛り上がらないし私は惹かれない。たとえ物語でも、悪さを開き直っちゃいけないんですよね。
——『PH』の敵も非常に存在感がありました。
上 荒木先生にはキャラやスタンドの絵を描いて頂いたんですが、すごい不思議な気がします。「これって荒木先生の設定を見て書いたものだっけ?」と、自分が考えたはずなのに自分のものでないような...。やっぱりこれが原作の力なんでしょうか?あと、小説の描写でキャラやスタンドのビジュアルを結構細かく書いていたんですけど、それをしっかり荒木先生が拾って下さって、それが驚きであり嬉しくもありました。
——西尾先生は以前、荒木先生と対談をされていましたよね?
西 確か「ジャンケン小僧は素晴らしい!」と延々とまくしたてていた覚えがあります。後から思い返して、なぜあそこまでジャンケン小僧にこだわったのか...もっと他に話すべきことがあっただろう、と (笑)。あと「3部が好きと言うと素人だと思われるから1部が好き」とか「ノベライズするなら2部」とか言っていましたね。あんなに力強く宣言していたのに、すっかり忘れてディオの小説を書いています (笑)。
——上遠野先生、荒木先生と『PH』について話される機会が今後あったらどうされますか?
上 もう、平謝りするしかないです (笑)。すいませんでした…って。それとも私もジャンケン小僧について語った方がいいですか?
「VS JOJO」、その黄金の未来ッッ!!
——お二人は普段の小説とノベライズで、作業や心情での違いはありますか?
西 小説を書くときは一回一回全て違いますから、むしろいつも通りだったかもしれません。
上 先ほども言いましたが、本当に楽でしたよ。全部原作という参考書があるので、攻略本を見ながらゲームするようなものです。アイディアに詰まっても全部書いていますから。逆に、これに慣れてはいけないと感じました (笑)。
西 ノベライズではよく「原作のイメージを壊さないようにすることが大変」といわれますが...それより僕は、週刊連載と同時並行のスケジュールが辛かった。『OH』では原稿をチェックしてもらっている間、『めだかボックス』のネームを描いたりしていました。それくらい追い詰められていたのですが、不思議なことに内容のクオリティは上がっていると自分でも感じました。危機感が出るんでしょうかね (笑)。
上 極限状態に追い詰められると能力が覚醒、とか。
——もし、もう一作『ジョジョ』を書くとしたら、何を書かれますか?
上 次回も『ジョジョ』とか...どれだけネタがない作家なのか(笑)。もし二作目があるなら、4部の仗助を題材にしたいですね。しかも私は仗助に対してちゃらんぽらんなイメージがあるので、話もきっとちゃらんぽらんにすると思います。
西 僕は連載中の『ジョジョリオン』がやりたいです。単行本1巻が出る前にノベライズを出したかった (笑)。あとはディオの部下で2部に生き残っていたゾンビの話とか、承太郎のラブコメ話とか (笑)。
上 そうなってくると、この後作品を書かれ舞城王太郎先生の題材が気になりますね。この前ちょっと小耳に挟みましたが...。
西 僕もちらっと聞きました。凄いところに目をつけてくるなぁ! ...と思いました。とてもこの場では言えませんが。
——それでは最後に、『ジョジョ』の魅力について語って下さい。
西 僕は『ジョジョ』をミステリーとして読んでいるところがあります。敵スタンドとい う謎が提示されて、名探偵ジョースター一族はそれをどう攻略するか...現象から敵の能力を推理して、それを解決する物語なんだ、と。推理小説好きの発言ですから鵜呑みにはできませんが(笑)、少なくとも僕が魅力を感じているのはその『謎解き』ですね。
上 『ジョジョ』はシリーズそのものが巨大なミステリーなんですよね。読者がそれを攻略できるか、常に荒木先生による挑戦が続けられていて...。そしてその謎は絶対に解けない!それが魅力でしょうね。私自身、実際に小説を書いてみての新発見はありませんでしたが、作品の深みや謎ばかりが増えた気がしています。でも、そこがたまらない!
——ありがとうございました。
注1) 1940年代にデビューし、推理小説・伝奇小説・歴史小説など多数の娯楽作品を発表してきた小説家。奔放な発想で忍者たちの戦いを描いた「忍法帖シリーズ」は特に人気が高く、幾度となく漫画化・映像化されている。
注2) 西尾先生が2006年に、『DEATH NOTE』(大場つぐみ・小畑健/週刊少年ジャンプ連載)のノベライズを手掛けたことを受けての発言。ちなみにタイトルは『DEATH NOTEアナザーノートロサンゼルスBB連続殺人事件』。